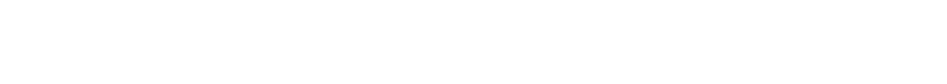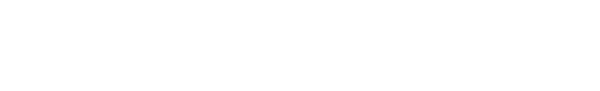WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 虹の女神』 柊坂明日子
-



第3回「みんな恋してる」
七月に入っても、まだ梅雨明けにはほど遠い、雨降りの日が続いていた。
結構な長雨にもかかわらず、楓子さんの家の夏野菜の生育は悪くなかった。
今日は霧雨が降っていて、気温はわりと低めで、楓子さん的には過ごしやすい。
「あのですね、転法輪さん、実は私、今ちょっと気になる人がいて、その人、アメリカの出版社にお勤めのバリバリのニューヨーカーなんです」
転法輪さんというのは、楓子さんのことだ。
その楓子さんのお屋敷に来て、今しゃべっているのは、翔岳館・輸入書籍編集部所属の川岸奈々子さんだ。出会った時まだアラサーだった奈々子さんも、今やもうアラフォーだ。でも相変わらず可愛くお洒落で、仕事もできる素敵な女性だ。
そこで、奈々子さんが愛用のエルメスのバーキンから取り出したのは、一冊の洋書だった。タイトルは『Horny lady starving day and night』。表紙には、熟女ブロンド美人がニューヨークの夜景をバックに、高層のオフィス内で鞭を口にくわえて妖しく手招きをしているイラストが描かれている。
「あ、これ『ニューヨーク毒魔女乱舞』の作者、トミー・ジェントリー先生の新作でしょう? Horny ladyだから、ムラムラした女性……そこにstarving、飢えている、ときてday and night、昼も夜も……。直訳すると『昼も夜も飢えている好色な女性』ね……でも、それじゃいまいちインパクトに欠けるから、私だったら『マンハッタン、濡れるオフィスで私を虐めて』かな……?」
この楓子さんは、今でこそ「ナイト・ハンター・ノベルス」で、SFバイオレンス・アクション・エログロ・超ハードボイルド作家として小説を書いているが、そのずっと前から隣の輸入書籍編集部「エグゾティック文庫」で、転法輪弘というペンネームで翻訳の仕事をしていた。
楓子さんは海外生活が長いので、英語、フランス語に堪能だ。それを活かして翻訳家となり、翔岳館の「エグゾティック文庫」で仕事をもらい始め、その関係で、翔岳館の絵本大賞の作品募集を知り、応募し、優秀賞に輝いたものの鳴かず飛ばずで、気がつくと亜蘭に声をかけられ、大河ショー和として男性向け小説も書くようになっていた。しかし、元をただせば翔岳館では、この川岸奈々子さんとの付き合いが一番長い。
「『マンハッタン、濡れるオフィスで私を虐めて』ですか!! それ、さっそく頂きますね。『虐めて』、がいいですね! 私も誰かに虐められた~い」
奈々子さんは、仮のタイトルをメモ帳に書き留める。
「あの……それ、私が訳していいの? っていうか奈々子さん今日、お仕事の話でいらしたの……?」
楓子さんは首をひねる。
奈々子さんは、プライベートで相談したいことがあると言って、楓子さんの家に遊びに来ているはずだった。
「えっと、あの……ごめんなさい……この本、転法輪先生に訳していただけたら、絶対、ヒット間違いないんですが……お願いできませんでしょうか……? この本の主人公の女性は、ごく普通の主婦だったんですけど、ご主人がある日突然失業して、一念発起した彼女がニューヨークに本社がある大手企業のお掃除担当係として働くようになって、初めはただ単に社内の掃除をしていたんですが、ゴミ箱から見つけた重要機密とか、密室の会議室で繰り広げられる男女関係とか、化粧室を掃除をしている時に、つい耳に入ってしまう、社員同士の会話とかで、会社の色々な事情を知るようになり、気がつくと、社長の秘書にまで上り詰めていく、かなり痛快なお話です。家では失業した旦那からDVを受けていて、しかもその旦那は浮気三昧、ご近所の奥様方からはマウントを取られさげすまれ、結構な年になった子供たちは、もう母親の言うことをきかないし、かなりクサクサした日を過ごしていたアラフォー彼女の、そのナイスバディをふんだんに使った作戦が、ぞくぞくしますよ」
「うわ……聞いているだけですごく面白そう。では是非、訳させてください。今、固定資産税を全額払っちゃったところなので、お仕事大歓迎です」
これから益々暑くなる夏場は、どうせどこにも出かけない楓子さんだから、家にこもっての翻訳のお仕事もまたきっと楽しい。
「で、さっき奈々子さん、気になる方がいて、その人、アメリカの出版社にお勤めのバリバリのニューヨーカーって言ってたけど……」
「そうなんです……。それがこの『マンハッタン、濡れるオフィスで私を虐めて』の翻訳本を、うちの『エグゾティック文庫』で出版してほしいって言ってきた向こうのエディターで、その彼と、頻繁にパソコンでリモート会議をしているうちに、なんかすっごく気が合っちゃって……」
「やだ、もう、桜川日名子先生にゾッコンの亜蘭編集長をはじめ、吉井くんも久しぶりの春が来てるし、その上、奈々子さんまで恋愛モードに突入なんて……そろそろ私も本気出して、素敵なお相手を見つけないと……みんなに置いていかれちゃうわ」
楓子さんは、冗談抜きで焦ってしまう。
「で、奈々子さん、そのアメリカンな彼、どんな人? 画像、ある?」
楓子さんがせかすと、奈々子さんはバーキンからうやうやしくタブレットを取り出し、ニューヨークの出版社にお勤めの編集者である彼の写真を、ドーーンと見せてくれた。
誰がどう見てもイケメン、爽やか。わざと無造作な感じにカットされた茶色の髪が相当お洒落だ。茶色のまつ毛もたっぷりと長い。年齢は、奈々子さんくらいのアラフォーか、ちょっと若い……? オフィスのデスクで、コーヒーの紙コップを握りしめ、茶目っ気たっぷりにウィンクしている。
「すごくいい感じ……。可愛いしカッコいいわ……仕事もできそう。でも、モテそうね……?」
奈々子さんは、大学の英文科を卒業しているので、彼との意思疎通に問題はない。
楓子さんは、そのタブレットに自分の親指と人差し指つけ、あちこち画像をどんどん拡大し、ついには机上にあったルーペで、さらにすみずみまでチェックする。
と、その時、
「あっ……」
と、楓子さんがつぶやいてルーペを机に置いてしまった。拡大された部分はそのままだ。
「え? な、何、どうしたんですか、転法輪さん……」
奈々子さんに不吉な予感が走る。
「いえ、何でもないの。何か……飲む? 白? 赤? 泡モノ……?」
「ちょっと転法輪さん、言って下さい! 今なら私、傷つかずにすみますっ。彼との交際はパソコン上だけなので、まだ、何も始まってませんっ! 中学生の恋愛以下ですっ!」
「う~~ん……奈々子さん……ごめんね……私、老眼だから、いつもルーペが必要で、家のあちこちに置いてあるんだけど、えっとほら、この彼の左手の薬指、ちょっとなにか線? みたいなものがチラッと見えない……?」
画像を拡大した上、ルーペを使わないと見えないレベルの線が確かにある。
「あああああ……」
奈々子さんが、ソファに深く沈み込んでいく。
「私……近眼の上に乱視入ってるから……よく見てなくて……ええ、これたぶん、指輪を外している痕ですよね……影じゃないもの……私、なんで気づかなかったんだろう……」
奈々子さんは、がっくりうつむいて、落ち込んでしまう。
「私ったら……よけいなことを……ごめんなさい、奈々子さん……。でも、もしかして指輪を外した痕じゃないかもしれないし、ひょっとして怪我して切った傷痕かもしれないし、今度とりあえず、リモートで会う時、聞いてみたら? でないと私、責任重大よ。間違ってたら困るわ……」
「いえ……私……つい、舞い上がって、彼、絶対シングルだって、思いこんでました。だって彼が、ナナコ、この夏は、ニューヨークにおいで、本物のナナコに会うのが楽しみだって……そこまで言われたらシングルかなって、思いますよね……」
楓子さんは、もう一度ルーペを手に取り、彼の左の薬指の線をチェックする。
見れば見るほど、指輪を外した痕だ。
楓子さんはこういう時、すぐ趣味の探偵業に走るミス・メープルとしての自分が、ほとほといやになる。
「転法輪さん、大丈夫ですからっ。私、もうアラフォーだから、失敗できなくて。ここである程度わかったことは、幸せだったと思います。でも、もしかして間違いもあるかもだから、一応、今度、彼が既婚かどうか直球で聞いてみます! なにげなく『バイ ザ ウェイ、アー ユー シングル?(ところでアナタ、独身デスカ?)』みたいなきき方で、いいですよね?」
奈々子さんは立ち直りが早かった。しかし英文科卒にしては、バイ ザ ウェイがちょっとカタイというか、とってつけた感満載だが、奈々子さんの直球勝負の決意はよくわかる。
「ということで転法輪さん、泡モノ、からの白でお願いします」
奈々子さんはタブレットをバーキンに戻し、言った。
泡モノとはシャンパン、白とは白ワイン。これから二人で二本飲むということだ。
「オッケーです。オーダー受けつけました。では、奈々子さん、レインコートを貸しますから、フードをかぶって、庭からバターレタスとプチトマト、他に目についた野菜、何でもお好きなものを採ってきてください。私はキッチンで、アサリのボンゴレ、ビーフカツ、等々、作ります。今、自家製ピクルスもいい感じで漬かってます。あと、シソかバジルがあったら、それも採ってきて下さい」
おいしいゴハンと飲み物、そして昔からのつきあいの仕事仲間が、きっと奈々子さんの悲しい気持ちをゆっくりと癒していくと信じて。