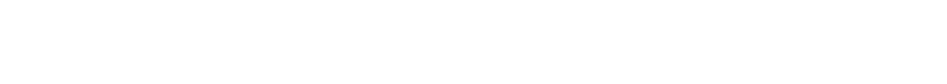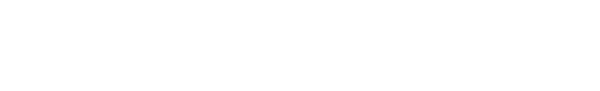WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 虹の女神』 柊坂明日子
-



第4回「夏まつり」
梅雨明け間近。
吉井くんの近況が、時々、楓子さんのパソコンにメールで送られてくる。
七月になってから例の着物の彼女と、入谷朝顔まつりと浅草寺のほおずき市へ行ったようだ。どちらの催しも楓子さんのお勧めだった。
彼女とは、会社帰りに神保町の例の和風喫茶で待ち合わせをするらしい。
吉井くんは今、恋愛で忙しく、楓子さん宅には足が遠のいている。
きっと、編集長の亜蘭さんも、作家の桜川日名子先生と楽しくやっていて、みんな夏の恋に忙しいのね、と、出遅れた感のある楓子さんは、少し寂しい。
こんな時、奈々子さんから頂いた翻訳のお仕事はありがたかった。孤独を感じず、ニューヨークにいるがごとくにわくわく訳しながら、日々を過ごすことができる。
と、その時、家の黒電話が鳴った。
受話器を取ると、
「転法輪さん、先日はありがとうございました~~。奈々子です。お仕事いかがですか?」
翻訳の進捗状況を聞くために連絡してきたのではないだろう、と楓子さんはすぐにわかった。
「どうしたの、奈々子さん。なんか元気そうだけど、いいことあったの?」
声色だけで相手の気持ちを読めるのが、楓子さんの特技だ。
「そうなんです! 例のニューヨークのエディター、既婚者でした! でも、そんなのはもういいんです! なんと、先生が今翻訳している本の作者、トミー・ジェントリー先生、この冬の来日が決まったんです! で、私、先生の接待役をおおせつかったんです! ジェントリー先生、バツ一ですけど、今、完全にシングルです!」
「やだーー、うらやまーー! この先生、著者近影の写真あるけど、すごいダンディーでカッコいいわよね? 私も会ってみたーーい!」
「実は私、ジュエントリー先生は転法輪さんに合うと思うんです!」
奈々子さんは、なんと彼を楓子さんに紹介するつもりだ。
「ダメよ、私なんてダメ、奈々子さんがいいわよ!」
「いえ、ジェントリー先生は前々から、転法輪さんにものすごい興味があったんです。ジェントリー先生の本は、なぜ日本の翻訳本が世界で一番売れているのかすごく不思議がってて、その翻訳者に是非会ってみたいっておっしゃってましたから!」
「そんな、ダメよ、だって私、この世田谷の家を捨ててニューヨークに行けないもの……。う~~ん、でももうこの際だから、世田谷の家を丸ごと売って、ニューヨーカーになっちゃおうかな……」
孤独が長すぎた楓子さんは一瞬にして、お祖父ちゃまが大事にしていたこの世田谷の大豪邸を売る気満々になっていた。
「ああ……でもダメ。奈々子さんが幸せにならないと、私が先になんて無理」
人の道を知っている楓子さんは、すぐに頭を冷やす。
「いえ、大丈夫ですっ。私、そこまで英会話が堪能じゃないから、英語を話しながらの結婚生活なんてイヤです……。日本で良い方を見つけますっ」
「そんな……奈々子さんは日本人じゃなくて、異国の人の方が合うような気がするんだけど……」
「いえ、やはり日本語が楽です……実は来週、某大手総合商社のアラフォー独身貴族たちとの合コンがあるので、そこに全力で焦点をあてていきます。もう私、前しか向いてないです!」
「すごいわ……さすが奈々子さんね……。わかった。私ももし、奈々子さんがお勧めしてくれるのなら、この冬、ジェントリー先生にお会いして、人生を変えてみる」
ようやく楓子さんにも春が来そうな兆しを感じる。
「吉井くんも亜蘭さんも頑張ってるし、私も自分磨きを頑張らないとね。やだ、私、カエデコ・ジェントリーになっちゃうのかしら……人生ってわからないものね」
「えっとあの、ところで亜蘭さんは、今、まったくダメです。例の桜川日名子先生って、実はご本人が書いてなくて、彼氏さんがゴーストライターだったんです。亜蘭さん、彼女のマンションでそのことを打ち明けられて、しかもムキムキマッチョな彼氏さんも同席で、二人からこれからもよろしくお願いしますって言われて、ふざけんなよって、編集部に戻ってきてから荒れてました。あと、吉井くんはこの頃、体調でも悪いのかしら……なんか、いつもボーっとしてて……」
亜蘭さんの事はさておいて、吉井くんが元気ないことに楓子さんは驚く。
だって、パソコンに送って来るメールには、朝顔まつりに行って帰りにウナギ屋さんに入ったとか、ほおずき市で彼女にほおずきの植木鉢をプレゼントしたとか、大雨の日、視界がすごく悪かったけど東京タワーに上ったとか、近々神宮の花火を見せたいとか、書いてあったのに……。
「この間なんて、吉井くん、会社が終わった後、神保町駅近くのコインパーキングでずっとしゃがみこんでました。で、声をかけようと思ったら、サッと立ち上がって、なんかニコニコしながらまた、駅の方に歩いていっちゃって……結局、声はかけませんでしたけど……」
「え……コインパーキングって、どこ……?」
楓子さんは、なんだか嫌な予感でいっぱいになる。
「ほら、転法輪さんと私がよく打ち合わせする、紅茶専門店がありますよね? あのすぐ先を、神田に向かって歩いていったところにある小さなコインパーキングです」
「あの界隈にコインパーキングなんて、あった……?」
楓子さんは、イマイチ位置がわからない。
「その駐車場、前は何軒か店があって、袋小路になっていたところなんですけど、一軒閉店し、また一軒閉店し……って、そんなことが続いて、五年ほど前にとうとう駐車場になっちゃったんです」
もちろん神保町だけではなく、今は東京中どこでも昔ながらの店が壊され、そこに新しいものが建てられたりと、景観は目まぐるしく変わり続けている。
「奈々子さん、連絡ありがとう。私、八月上旬までにジェントリー先生の翻訳、仕上げちゃうわね」
楓子さんは、ざわざわしたものを感じながら受話器を置いた。
そしてすぐパソコンに向かい翻訳を続ける……のではなく、前々からどうも気になっていたことを、次々と検索し始めていた。
*
その二時間後、午後六時。
うっすらとした霧雨の中、楓子さんは神保町にいた。そして奈々子さんが言うコインパーキングを見つけると、そこでずっとたたずんでいた。傘はささずレインコートのフードをかぶっている。それで充分、霧雨はしのげる。
時は十分、二十分、三十分、そして一時間、二時間、三時間と過ぎてゆく。
とうとう午後九時を回って、人通りもどんどん少なくなっていったとき、見慣れた顔の男性が、楓子さんに向かって歩いてきた。
「吉井くん!」
楓子さんは手を振ったが、吉井くんは気づきもしないで、楓子さんの横を素通りしていく。
「えっ?! ちょっと、吉井くん、大丈夫? 私よ? わかる? 楓子よ」
楓子さんは、吉井くんの腕をつかんで言った。
「えっ、あっ、せ、先生っ! どうしたんですか、こんなところでっ、傘もささないで」
「吉井くんこそ傘もささないでどうしたの、ボーっとして」
「ええっ? 僕、ボーっとなんてしてませんよ……えっと、僕は彼女に会いに……」
「彼女って、誰……?」
「えっと……名前……なんだっけな……」
「名前も知らないでおつきあいしているの? そんなのおかしいでしょう?」
「えっ、でも僕、これから、ここの『松埜庵』で、彼女とお茶するんです……」
「吉井くん、『松埜庵』ってどこにあるの? 前に言っていた例の和風喫茶のこと?」
「ええ……僕……そこの抹茶セットが好きで……彼女も、そうで……」
楓子さんは、ゾッとした。そして吉井くんの顔を見て、彼の目の前で、パンパーンとかなり強く手を叩いた。まるで神社で柏手を打つようだ。目を覚ませ、ということなのか……。
そしてすぐその後に、
「臨、兵、闘、者、皆、陳、列、在、前!」
なんと楓子さんは、両手の指を複雑に組み合わせる型の九字を切った。真言宗の災厄を除くための呪法である。
すると、吉井くんは一瞬にして、ハッとした顔に戻る。
「え? 楓子さん、なんでここに?」
「吉井くん、あのね、『松埜庵』さんはもう何年も前に、神保町のお店を閉めているのよ。その右隣にあった額縁屋さんも、左隣の下駄屋さんも、みんなもう、ここにはないの。で、その場所に今、このコインパーキングがあるの。つまり、ここよ」
「え……僕……どうしてここにいるんですか……?」
吉井くんは、薄暗いコインパーキングをぐるりと眺める。そして、ようやく鞄から折り畳み傘を取り出し、楓子さんに差しかけた。この気遣いは、いつもの吉井くんだ。
「ごめんね……こんなことを言って……でも、私が思うに……吉井くんは、何かに化かされているとしか思えないの……」
「僕が、化かされているんですか……?」
「よく、わからないけど、吉井くんの彼女は実在する人じゃないような気がして」
「そんなことはないですよ。僕、彼女と朝顔まつりに行って、入谷でウナギを食べましたし、浅草寺のほおずき市では、彼女にほおずきの鉢をプレゼントしましたし、その鉢には金魚の絵柄の風鈴もついていて……ほら、万年筆だって頂いた」
そう言って吉井くんは、すぐに背広の内ポケットに手をのばした。
「あれ……おかしいな……いつも内ポケットに入れているのに……あ、そっか、会社の引き出しに入れてきちゃったんだな……」
「この間も吉井くん、その万年筆、会社の引き出しに入れてきたって言ってたけど、大好きな彼女から頂いた大事なものだから、肌身離さず内ポケットに入れているはずよね……? そういうの、会社の引き出しになんて入れないでしょう?」
「そういえば……僕……彼女の住んでいるところも……名前も……知らない……。会うのはいつも、夜になってから……しかもこうして雨が降っている時ばかりだ……」
吉井くんはどんどん正気に戻っていく。
「ねえ、吉井くん、この一、二か月で、どこかなんとなく気が悪い場所とかに行った? たとえば、場末の喧嘩が絶えない、いかにも治安が悪そうな飲み屋さん街とか、もろもろの訳あり男女がひしめくホテル街とか、あるいは夜の墓地近くを歩いたとか……」
「いえ……ないです、ないです。会社と家の往復と、たまに先生の家に遊びに行くだけです。しかも僕、春にはこんぴらさんと善通寺にお詣りして、それ以降、超絶好調だったじゃないですか……」
気がつくと、吉井くんの顔に赤みがさしていた。先ほど出会った時はどことなく顔色がすぐれなかったが、今の顔つきはいつもの吉井くんだ。
何かようやく長い催眠から解けたような表情をしている。
「何やってるんだろう、僕は……。あっ、それより先生、僕がおかしいから心配して、こんな遅くまで、ずっとここで待っていてくれたんですかっ?」
「ええ……奈々子さんから、ちょっと吉井くんの様子を聞いて……すごく気になって。『松埜庵』のことが決定的だったわ……調べたら、もうその店は神保町にないってことがわかって……」
「ああ……すみません、先生……僕……ホントに……バカで……」
「バカじゃないわよ……吉井くんは優しいから、霊界の人たちもついつい吉井くんにちょっかい出したくなっちゃうの……」
「えっ!! 彼女、霊界の人だったんですかっ!!」
吉井くんは根本のところで、何が起こったのか、わかっていなかった。化かされるというのはそういうことだ。
「うわーー、こわいーー、僕、もしかして、霊界の彼女とおつきあいをしてたんですかっ?」
思い返せば、吉井くんはスピリチュアル系がとにかく弱い人だった。
「ほら、今、東京のお盆だし、色々な霊があちこちに出没しやすくなっている時期だからね? これは八月中旬頃まで続くのよ。夏の風物詩よ?」
「ああ……困ったな……僕……憑りつかれてたのかな……。あ、でも、今年のお盆は、僕、また四国の実家に帰ろうと思って……。ここ何年も、きちんとお盆に帰ってお墓参りをしていなかったから、今年こそちゃんとしようと思うんです。だからその時また、こんぴらさんと善通寺にお詣りして、しゃっきり気合を入れてもらおうかな……」
吉井くんは香川県讃岐の出身だが、先祖代々のお墓は、瀬戸内海の香川県に属する小さな過疎の島に勢ぞろいしている。ご先祖様は島の出身なのだ。
「うちの島の夏祭りっておごそかで、いいですよ。盆踊りがあったり、新盆の霊を弔って送る精霊流しをしたり……」
*
八月十六日。
朝早くに新幹線に乗った楓子さんは、お気に入りのヴィトンの巾着リュック型、その名も「遠足」という意味の「ランドネ」を背負って、今回はちゃんと指定席をとり着席すると、新横浜駅では崎陽軒のシウマイを手に入れ、今は名古屋の天むすに舌鼓を打っていた。
「これってなんか……完全にデジャブですよね……三月に里帰りした時と、全く同じシチュエーションだ……」(※ミス・メープル『瀬戸内海の秘密』をご参照ください)
吉井くんは、自分の担当作家が新横浜駅や名古屋駅で無謀にも下車し、猛ダッシュでキオスクに突っ込み、おつまみを買ってまた新幹線に飛び乗ってくるたび、心臓が止まりそうになる。
そして今回、取材ではなく、すっかり四国の大ファンになった楓子さんが、翻訳の仕事も終えたところなので、夏の想い出作りに吉井くんの帰省にくっついて、またまたお気に入りの香川県を目指していた。
「でね、吉井くん、聞いて。亜蘭さんったら、イギリスに行くならダートマスの海軍兵学校を取材してきなさいよ、って簡単に言うけど、あそこ誰でも自由に入れてくれるところじゃないのよ……こういう時、知り合いのつてがあれば見学させていただけたかもしれないけど……」
楓子さんは、空になった吉井くんのプラスチックのグラスに、赤ワインを注ぐ。
「あ、先生、僕そんなに飲めないです……」
と言ってるのに、楓子さんは持参のワインをお勧めする手を止めない。
「大丈夫よ、ほら、天むすが喉につまっちゃいけないから、お水がわりと言うと過激だけど、赤ワインはポリフェノールがたっぷりで体にいいから、召し上がってね?」
まだ午前九時前だが、旅は楽しくがモットーの楓子さんは気にしない。
「楓子さんのお父様が生きてらっしゃったら、ダートマスの海軍兵学校も、見学できたでしょうね。あちらにお知り合い多いでしょう?」
楓子さんのお父様は、その昔、イギリス駐在の大使だった。
「そうね……そうだけど……もうみんな亡くなってしまったものね……誰にも頼めないわ。後は自力で生きていくだけ」
お父さん子だった楓子さんは、しょんぼりしてしまう。
「海軍兵学校っていえば、うちの父方の曾祖父が、広島の江田島の海軍兵学校に行ってましたよ。まあ、ダートマスと日本の海軍兵学校だと、ちょっと違うかな?」
そう言ってから、吉井くんが天むすを一口食べる。
「ちょっと、吉井くんっ!!」
楓子さんの顔色が、かわっていた。
「えっ、この天むす、食べちゃいけなかったですかっ?」
吉井くんは一口かじった天むすを、元あったパッケージのところに戻そうかどうしようか、おたおたしている。
「天むすじゃなくて、吉井くんの曾お祖父ちゃま、江田島の海兵卒だったの? そんなの初めて聞くわよ」
「今、初めて言いますから……」
「なんでもっと早く言ってくれないの? 私が海兵マニアって知ってるでしょう? 世界三大海軍兵学校って、ダートマス、江田島、アメリカのアナポリスよ。そんなすごいところに曾お祖父ちゃまが行ってたなんて、それ知ってたら私、お会いしたかったのに!」
「だって僕、先生が海兵マニアって知らなかったから。帝国海軍がお好きなのは、うすうす知ってましたけど……だってペンネーム『大河ショー和』ですから。戦艦大和、好きですよね?」
「曾お祖父ちゃまのツテがあれば、江田島見学も可能だったのに……『新宿魔法陣妖獣伝⑤』で海上自衛隊のネタ、満載だったでしょう? あの広島にある海上自衛隊の場所が、江田島の旧海軍兵学校なの。昔の建物もほぼ残っているのよ。あそこさえ見学していたら、もっとリアリティのある文章が書けたのに」
「いや先生、あそこ普通に見学できますよ……」
「違うの、知り合いがいると、もっと普通では見せてもらえないところも、ちょこっと見せてもらえるかもなの」
「ああ……でも、曾祖父は『武蔵』に乗ってて……レイテ沖決戦に向かう途中で亡くなってますから、僕も会ったことがないです……すみません……」
「えええええ~~~~戦艦『武蔵』に乗ってらしたの! 吉井くんのことは、ほぼほぼ何でも知っていると思っていたけど……こんなコアな情報を知らなかったなんて、もうやだ……」
楓子さんはかなりのショックで、今、天むすを食べる箸が完全に止まっている。
「生きていたら、今、百歳を越えてますし……」
そう言うと、吉井くんはスマホを取り出し、画像を開く。
「前に……たまたま実家で、その曾祖父の制服姿の写真が出てきて、僕、撮ってきましたよ。えっと、ほらこれ……」
吉井くんが見せてくれた画面には、海軍兵学校の白い夏の制服を着ている曾お祖父さんの姿がモノクロで現れた。丈の短い詰襟のジャケット。恐らく金色であろうボタン、同じく白い制帽の正面には錨のマーク。
「やだ! 曾お祖父ちゃま……吉井くんにそっくりじゃない……めちゃくちゃハンサムよね……モテたわね……」
「モテたかどうかは知りませんが、似てますよね? だから僕もびっくりして、思わず撮っちゃったんです」
「この曾お祖父ちゃまがいて、今の日本があるのよ……日本のために戦ってくださったのよ……。今日これから島に渡ったら、是非、お墓参りをさせてね?」
「ありがとうございます。あの……海軍兵学校って縦横の絆が強くて、うちの曾祖父は若くして亡くなってますけど、まだご存命の後輩の方とか紹介できますよ。でも、急がないとですね。一番若い方でも九十代前半ですから」
「そうなのよ……なんで寿命ってこうも短いのかしら……私、百五十歳くらいまで元気で生きることができたら、まだまだ色々とやりたいことがあるけど……そうはいかないのが人生よね……だから毎日毎日がとっても大切……」
楓子さんは、しみじみと言った。
海兵話で延々と盛り上がるうちに、新幹線のぞみは、あっという間に岡山へと到着した。そこから土讃線に乗り、揺られること四十分たらずで二人は香川県丸亀駅に着いていた。
フェリーの時間まで、駅周辺のおいしいうどん屋さんに行ったり、骨付き鳥の店に行ったり、今は銘菓「かまど」の喫茶店でお茶をしている。
楓子さんは久しぶりに夏を満喫していた。四国の夏は灼熱の暑さだが、東京の暑さと質が違うのか、べとつき感がなく、じりじり焼けつく感じは苦ではなかった。
「ここのお抹茶セットもいいですよね……。あ、『も』って言っちゃった……」
吉井くんは、和風喫茶「かまど」の抹茶セットを前に、ついうなだれてしまう。
神保町の幻の「松埜庵」で、抹茶セットを頼んだことが、つい昨日のように思い出される。
けれどあの着物の彼女は、楓子さんが吉井くんの目を覚まさせてから、二度と現れることはなくなってしまい、もうひと月が経つ。
「先生、幻の着物の彼女ね、僕が会社の話とかすると何でも『そうなの? そうなの?』って楽しそうに聞いてくれてね、僕……楓子さんとの仕事のことも色々話しましたよ。素敵な先生がいて、書かれる本がホントに面白くて、僕、その先生の担当させて頂いてとてもやりがいがあるんですとか、その先生の家でよくご馳走になるんですとか、庭の野菜がおいしいとか……猫のシンプキンがなついてくれるとか、そんな自分の事ばっかり話して……僕、彼女のこと、まったく聞いてあげなかった……聞かなくても、なんか知っているような気もしたし……」
「私も、ごめんね……強制的に別れさせてしまったような気がして……。その彼女もなんらかの事情があって、吉井くんの前に現れたと思うから、それもよく考えてあげればよかったと思って……」
実は楓子さんは、吉井くんが今でも落ち込んで傷心なのではと心配して(通常、夏に旅行はしないのだが)なんだか気になって、今回、わざわざ吉井くんの帰省についてきている。
「でもね、先生。僕、彼女と会えて、なんか幸せでしたよ。優しい気持ちになれるっていうか、ほっとするっていうか……」
言いながら、吉井くんは腕時計を見た。
「あ、そろそろ行きましょう? もうすぐフェリーの時間ですね……」
楓子さんと吉井くんは、丸亀駅前商店街で、お墓参り用の花束をたくさん買い、船に乗り込んだ。
*
吉井くんの故郷の島に着いたのは、その三十分後、午後四時だった。
フェリー乗り場のすぐ横に島を巡回するマイクロバスがあって、二人はそれに乗って島の共同墓地へと向かった。
お墓参りの基本は、午後三時くらいまでがいい。夏は日が長いので四時過ぎでもまあまあ許せるが、あまり遅くなってからだと、また妙なものに出逢ってしまう。
「でも、今日はお盆の送り火の日ですから、お墓参りが遅くなっても大丈夫です。大勢、お参りに来てますから」
その言葉どおりに、吉井一族が眠るお墓周辺には、島のみなさんもご先祖様のお墓参りに大勢が集まっていた。みんな、夜の盆踊りを楽しみにしている。
そして、楓子さんが戦艦『武蔵』で亡くなった吉井くんの曾祖父のお墓の前にたどり着くと、そこにはもうすでに、たくさんのお花がお供えされていた。たぶん一足先にお参りをした、吉井くんのご両親と祖父母からであろう。
楓子さんは花瓶の若干空いたスペースに、菊やらカーネーションやらアヤメやらを生けた。
「わあすごい、さらに立派になりましたね。曾お祖父ちゃん、嬉しいだろうなあ」
吉井くんは、目を細めてお墓を眺める。
「『かまど』の和菓子も持ってきたの……お供えさせてね……」
楓子さんは一番人気の、その名も「かまど」という銘菓をお供えして、両手を合わせた。
とその時、どこからかフワっといい香りがしてきた。
楓子さんと吉井くんは、同時に顔を見合わせた。
しばらく二人とも黙って、その香りの出所を考えていた。
楓子さんは、抱えていた大きな花束の中に顔を思い切り近づけた。
「この中かしら……」
吉井くんは吉井くんで、お墓にお供えした仏花に顔を近づける。
「あっ……」
楓子さんと吉井くんは、同時に気がついた。
「先生、この花です、これ!」
吉井くんは、お墓の花瓶に生けたアヤメを指さした。
「その通りよ、私もこの花束の中の、アヤメからあの香りを見つけたわ」
あの香りとは、梅雨の夕暮れ、楓子さんの家近くで落雷があり停電した時にかいだ、スミレのような石鹸のような、それでいてウッディな香りだった。
「ああ、そうか、亜蘭さんがつけていたエルメスのオードトワレ、『イリス』っていうの。イリスってフランス語よ。英語でアイリス、アヤメのことよ。そうか……このアヤメの香りだったのね……私としたことが、今の今まで気がつかなかったわ……」
と、その時、楓子さんが、お墓の横に彫られた文字に目をやる。
令和四年三月二十一日没 享年九十八歳――。
「ちょっ……吉井くん、この方……春に亡くなったばかりじゃない……曾お祖父ちゃまの奥様……でしょ? えっ……吉井……アヤメ……さん……っていうのっ!?」
「ええ……そうなんです。僕、この春に先生と、島に来たでしょう? 実は曾祖母は、僕らが帰った翌日に亡くなってしまって、僕、改めてまたここに戻るってできなかったんです。あの頃、校了とかでめちゃくちゃ忙しくて……。うちの両親も、帰らなくていいよ、もうすでに来てくれたからね、曾お祖母ちゃんもわかってるよって言うから……。僕、お花を送っただけで……。曾祖母は長いこと施設で寝たきりだったんです。誰が来てももう何も認識できなくて、僕も曾祖母を最後にお見舞いしたのが大学を卒業したあたりで、その時ももう、まったく意思の疎通はできないような状態で……ずっと眠ってました。小学校の頃はよく話したけれど……結局、ずっと疎遠でした……。でも、お葬式……出ればよかったな……。結局、身内だけでひっそり送ることになってしまって……寂しいお式にしちゃったと思います……」
吉井くんの胸に、急に後悔が押し寄せてくる。
「吉井くん……ほら、あの……万年筆……」
「ええ……黒の蒔絵の万年筆でしたけど……金で菖蒲の花が描かれていて……それが?」
「吉井くん……菖蒲って、アヤメのことよ……」
楓子さんが言うと、吉井くんが息をのんだ。
「曾……お祖母ちゃん……だったんですか……?」
その瞬間、吉井くんの目に涙があふれてくる。
「そっか……そうなんだ……だから、ちっとも怖くなかったんだ……。楓子さん、言ってましたよね……身内だと幽霊になっても怖くないって……。本当に……僕はだめだな……やっぱりお葬式……出ればよかった……。僕……曾お祖母ちゃんを、寂しく旅立たせてしまったんだ……」
「そんなことないわよ……きっと自慢のひ孫だったのよ。しかも、曾お祖父ちゃまにそっくりだし、気になったのね。吉井くん、曾お祖母ちゃん孝行をしたわよ。入谷の朝顔まつりとか、浅草寺のほおずき市に連れて行って、東京タワーも上ったのよね? 抹茶セットもご馳走して、ウナギも食べて、曾お祖母ちゃま、楽しかったと思うわ」
「そうでしょうか……」
吉井くんはうなだれたままだ。
「そうに決まってるじゃない。しかもほら、こうしてちゃんと新盆のお墓参りに来てくれて、嬉しくないはずがないのよ。精霊流しをするために、今日こうして戻ってきたんでしょう? しかも、こんなに花があるのに、今、香っているのはアヤメの花ばかり。『遼、ありがとう、気づいてくれて』って言ってるのが、私にはわかるわ」
「ホントですか……?」
吉井くんの涙が、お供えのアヤメの花にぽとぽと落ちる。
「僕、先生とここに来てよかった……じゃないと、絶対に気がつかなかった……」
「ええっ!? そ、それより吉井くん、ちょっと後ろ後ろっ、見てっ!!」
目をまん丸にした楓子さんが、海の向こうの瀬戸大橋を指した。
なんとそこには、くっきりとしたみごとな虹がかかっている。
「うわ……すごい……僕、何度も何度もこの島に来ているのに、瀬戸大橋にかかる虹なんて、見たことないです」
吉井くんは、ようやくここで涙をふいた。
「吉井くん、『イリス』って、ギリシャ神話の虹の女神で、神様のお使いなのよ、知ってた?」
「そうなんですか……初めて知りました……。やっぱり先生は、ミス・メープルですね。かなわないです……全部、謎が解ける……」
……遼は大きくなったら、東京に行くの?……
……まだわからんけど、東京か京都の大学に行きたい……
……ええわね、ひいばあちゃんは、東京に行ったことがないのよ……
……僕が東京に行ったら、ひいばあちゃんを東京観光につれてってあげるね……
……それは楽しみだわ……長生きせんとだめね……
……うん、ぜったい長生きして、ひいじいちゃんの分も……約束だよ……
……うん、約束ね……
楓子さんは吉井くんのスマホを手にすると、吉井くんとそのバックに映る虹の写真を急いで撮った。
曾お祖母ちゃまとの素敵な思い出が消えないうちに――。