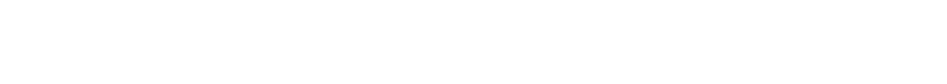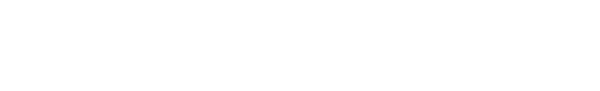WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 虹の女神』 柊坂明日子
-



第2回「袋小路の甘味処」
それから数日後、梅雨の晴れ間に、楓子さんは東京は千代田区、神田の神保町へと赴き、古書店めぐりをしていた。ここには世界最大級の規模をほこる古書店街がある。とはいえ、楓子さんが行くところはいつも決まっている。海外の児童図書や絵本が豊富に取り揃えてある古書店だ。
タイガーショーは、今でも心は絵本作家――世界中の素敵な絵本に心が躍る。そして今日も掘り出し物を何冊か見つけ、大満足で店を出ると、
「わっ、な、何っ、楓子さん、どうしたの、こんなところで? 吉井と打ち合わせ?」
翔岳館「ナイト・ハンター・ノベルス」編集部の編集長、亜蘭明氏と大通りで鉢合わせだ。翔岳館はこの通りから目と鼻の先なので、こういう出会いは珍しくない。亜蘭さんは楓子さんよりちょっと年上のアラフィフ。今日はパリっとした夏物スーツに、かなり気合を入れたブランドものの高級ネクタイをしている。
「えっと、あの……ご無沙汰しております……。いつも、大変お世話になっております。今日はちょっと……ワタシ……絵本を探しに……」
楓子さんが絵本と言った瞬間、編集長は苦笑いをした。アナタまだ絵本から足を洗ってないんだ――というようなため息まじりの視線。
この亜蘭さんは元々、翔岳館の児童文学編集部・絵本チームの副編集長をやっていて、さかのぼること十四年ほど前、楓子さんはその翔岳館児童文学賞・絵本部門で優秀賞に輝いていた。
その時、他の選考委員はまったく楓子さんを推してくれなかったのだが、亜蘭だけが楓子さんの才能を見抜き、絵本作家としてデビューさせてくれた。
デビュー作『ウサクマちゃんの冒険』が出版され、楓子さんはとにかく嬉しかった。そしてやる気いっぱいですぐに第二弾を描き上げたが、それはまったく出版化される方向へは進まなかった。
この受賞作の『ウサクマちゃんの冒険』は、ウサギとクマが魔法の国を冒険する、ほっこりしすぎの物語だが、この時、同時にデビューした高校生の女の子の大賞作品が大きく取り上げられすぎて、楓子さんの作品はかすんでしまった。デビュー作が売れないと第二弾などとても出せないのが、出版界の現実だ。
しかし、それから数年して、亜蘭は児童文学編集部から今の「ナイト・ハンター・ノベルス」へ異動になると、ひょんなことから楓子さんに再会し、彼女にSFバイオレンス・アクション・エログロ・超ハードボイルド作品を書かせてみるという荒業に出た。そして今や楓子さんは「ナイト・ハンター・ノベルス」きっての稼ぎ頭だ。
稼ぎ頭なのだからもっと胸をはってえらそうにしてもいいものを、楓子さんは亜蘭の顔を見ると未だに緊張が走る。彼には自分を絵本作家としてデビューさせてくれた恩義があるため、とにかく頭があがらない。律儀な楓子さんにとって、亜蘭は神様レベルの恩人なのだ。
それを知っての亜蘭も、楓子さんに対してはいつも塩対応だ。楓子さんが自分に恩義を感じてビビッているのをいいことに、ついついぞんざいな口ぶりになる。
「楓子さんさあ、絵本もいいけど引き続き『新宿魔法陣妖獣伝』も頑張ってよね。そろそろ九巻目を書いたらどう? 来年の固定資産税のために頑張らないと、せっかくの世田谷の家、切り売りしたくないでしょう? あ、そうだ。アナタ、なんか新シリーズをイギリス舞台にして書くとか聞いたけど、取材費、あんまり出さないからね。吉井と二人でナップザックしょってイギリスを歩いて縦断するくらいの気持ちでいてよ」
編集長は、楓子さんをいつも初心に戻してくれる稀有な方だ。どんなにドル箱作家となっても、一瞬にして楓子さんの自己肯定感をどーんと下げるテクニックに長けている。亜蘭の前では、楓子さんは永遠のド新人だ。
「ナップザックですか。昭和な言い方ですね……ナップザック……ナップザック……私でさえ古く聞こえるわ……ごにょごにょ……」
楓子さんは、うつむきながらモゴモゴ愚痴っている。
「……っていうか、ナップザックってドイツ語よね。リュックサックもドイツ語。英語だったらデイパックかバックパック……。イギリス縦断するのにナップザックって、どんだけ身軽なの……? それって、しばりヒモつき簡易背負い巾着袋よ? それだったら私は、機能性の高い長期の旅行用のアメリカ製のバックパックを買って出かけるわ。いえ、旅行だもの。ここはビシッとヴィトンのランドネを背負って、サムソナイトのスーツケースを持ってスイスイ行くの。キャスターつきで、どこへでも楽々移動よ。一番大きなスーツケースを買って、帰りにはロンドンの王室御用達高級自然派スーパー『ウェイトローズ』で、ジャムとかチーズとか紅茶……あとクッキーとかチョコも大人買いよ……」
「ちょっと楓子さん、どうしたの、さっきからうつむいてブツブツ言ってるけど、俺の話、聞いてる?」
「あ、いえ……イギリスは……やめます……。新シリーズは、私には荷が重いかな、と……今……気がつきました」
楓子さんは、神保町駅近くの大通りに一人立つそのあまりの居心地の悪さに、急になにもかもがしんどくなっていた。緊張感がMAXになるとよくあることだ。
「えっ!! そ、そんなっ、イギリスに行ってらっしゃいよっ! 大河先生だったらきっとまたほら、MI6がらみのスパイを使って、その男が日本の海上自衛隊の本部に切り込んでいったり? そうだよ! イギリスは海軍のメッカだったよね? 楓子さん、海軍好きだよね? ダートマスのイギリスの海軍兵学校を取材してらっしゃいよ!」
亜蘭はここでようやく、ひょっとして自分はドル箱作家のキモチをかなりないがしろにしてしまっているのではないかということに気がついた。
相手がまずめったなことで怒らない楓子さんだけに、気を遣わず、好き勝手にしゃべりすぎていた。亜蘭は他の作家の先生にはグチらないが、楓子さんだけには常に塩対応でストレス発散させてしまうことに、今、大反省だ。もしかしてモラハラで訴えられてもおかしくないかもしれない。
「いえ……もういいんです……それにダートマスの海軍兵学校なんて軍事機密がてんこ盛りで、誰かの紹介がないと絶対中に入れてもらえないから……私みたいな女じゃムリ……」
亜蘭の圧力が強すぎたのか、今やもうなげやりになっている楓子さんだ。ナップザックが致命傷だったらしい。ムリ、といい始めると、とことん沈んでしまう。
「えっと、あの、ちょっと待ってね、楓子さん。ほら俺、今、吉井呼ぶから。この近くに超有名老舗紅茶店あったよね? あそこでアナタの大の仲良しの吉井クンと、ステキなティータイムしてケーキとかも食べちゃって、帰りにはそのお店の高級茶葉もたーーくさん買って帰ったらどうでしょう? モチロンぜんぶウチもちです! あああ、まだそこにいてね? ――あ、もしもし吉井クン? 今、大河先生、神保町にいらしてるから。いつもの老舗紅茶店で、おいしいものご馳走してあげてね。お帰りの際は、お土産の茶葉もお持ち帰り頂いてね。えっとほら、イギリスの取材の話、具体的に決めたり? 素敵な可愛いホテルとかも選んで差し上げたり……? ウチもちでハロッズで大人買いもオッケーです! 吉井~~よろしくね~~頼むよ~~。うちの編集部は吉井クンでもってま~~す!」
亜蘭は、楓子さんとの話の途中でスマホを取り出し、会社にいる吉井くんを呼び出していた。
「きっともう……『ウサクマ』ちゃんの第二弾は永遠に無理なのね……。スピリチュアリストの江原啓之さんが前に『天職』と『適職』は違うって言ってたのって、このことね。天職とは心と魂が喜ぶこと……。けれど自分の好きなことをする天職はお金にならないって……。適職っていうのは経済活動……。自分自身の持てる技能を提供して、その代償としてお金を得るの……。そして、適職であるタイガーショーとして、私は今でもあの世田谷のお屋敷に住むことができる……」
楓子さんは引き続き神保町の大通り沿いの歩道で、こんな深いことに気づかせられていた。
「あ、じゃあ、楓子さん、俺、これから桜川日名子先生の家に、打ち合わせに行くから。桜川先生の家って六本木のタワマンで、夜景とか超キレーなの。っていうか部屋も超モダンで素敵で……家にバーとかもあってさーー。たいがいズージャー(ジャズ)が流れてるんだよねーー。俺、これから明治屋さんに行って、シャレオツなシャンパンでも買っていかなきゃなんだーー」
桜川日名子さんとは、楓子さんと同じくナイト・ハンター・ノベルスで書いている作家さんで、まだ作品はそれほど売れてはいないが、ものすごいナイスバディのアラサー美女で、その美女が割と過激なロマンス・バイオレンス・ミステリーを書くのがネタ的に面白いらしく、よくマスコミに取り上げられている。タワーマンションは、ご実家のご両親が不動産業をやっていて、その流れで買ってもらったものらしいが、亜蘭はもう桜川先生にメロメロだ。
そういうことで今日の亜蘭は、上から下までキメに決めたブランド・ファッションに身を包んでいた。彼はアラフィフでバツ3だけど現在シングルだから、恋愛は自由だ。
「では私、お言葉に甘えて、紅茶、ごちそうになりに行きますね……吉井くん、来てくれるのかな……忙しいんじゃないかしら……ホント言うともう帰りたい……」
楓子さんは頭を下げて、しょんぼりといとまごいをする。
と、その時だった。亜蘭からフッといい香りが漂った。
お気に入りの作家さんとの打ち合わせだと、香水までつけるようだ。
「あ……その香り……」
楓子さんは、小首をかしげた。どこかで嗅いだ香りだ。
「えっ、もしかして、俺のオードトワレの匂い、きつかった?」
亜蘭さんは焦って楓子さんに聞く。
「いえ、とてもいい香りです……実はこの香り、つい最近、嗅いだ記憶があって……」
吉井くんとキャンドルをともし、ディナーを食べている時だ。
「え? ホントに? ねえねえ俺、臭くないよね? この香り、大丈夫?」
「ぜんぜん大丈夫です。素敵な香りですよ。スミレのような……石鹸のような清潔な……それでいてどこかウッディで……落ち着きます……」
「うわーーーー、さすがタイガーショー、鼻もいいねーーーー。実は俺が今つけてるのって、エルメスの『イリス』っていうオードトワレ。ほら、このネクタイ見て? 実はこれもエルメスのタイ。今日は俺、エルメス・デーなんだーー」
「ああ……エルメスでしたか……いつもと違う、かなりお洒落で素敵なタイだなって思ってました」
「ホントに? 楓子さん、俺にヨイショしなくていいからね? ヨイショしても、『ウサクマちゃん』の第二弾、まだ出せそうもないから……」
やっと亜蘭が申し訳なさそうに言った。
「いえ、もういいんです……江原さんが……言ってましたから……天職と……適職は……」
「あっ、楓子さん、じゃあ俺、タクシー拾うから、行くね。イギリス頑張って!」
エルメスな彼は、楓子さんの話の途中で、鮮やかに神保町から消えていった。
*
亜蘭と別れた楓子さんは、そこから五分ほど歩いた老舗紅茶専門店に行くと、セイロン・ロイヤルミルクティーをポットで頼んでいた。
美しいカップに注がれた紅茶を一口飲むと、生き返る思いだ。
ほどなくして、吉井くんが駆けつけてくる。
「楓子さん、お待たせしました。あの、亜蘭さんが、いきなり慌てて電話してくるから……きっとまた、楓子さんになんか失礼なことを言ったんじゃないかと思って……先生、大丈夫ですか……?」
吉井くんは、店につくやいなや担当作家の心配をする。
「いいの、私、タイガーショーで稼がせて頂いて、今の生活が成り立っているの。私に厳しく接してくれるのは、亜蘭さんくらいのもの……だから私、イギリス取材旅行はナップザックをしょって、イギリス全土を自分の足で歩いて見て回ろうと思うの。そのくらいの苦行を積まないと、次また面白いものを書くなんてできないのよ。それを亜蘭さんは私に言いたかったんだと思うわ……」
楓子さんが真剣に話していると、ウェイトレスさんがきて、吉井くんにオーダーをたずねる。
「あ、じゃあ僕は、セイロン・ウバをお願いします……あと、スコーンを二人前お願い……」
します、というところで、
「吉井くん、私、スコーンはいいわ……大丈夫……もうそんな贅沢できないもの……。私、今まで翔岳館にお世話になりっぱなしだったから、これからは作家としてもっと、つつましやかな生き方をして御恩返しをしていきたいと思ったの……」
ナップザックに衝撃を受け、楓子さんの中で何かが変わりつつあった。
「でも、先生、ここのスコーンお好きでしたよね? ほら、本物のクロテッド・クリームを出してくれるお店って、東京にはそんなにないし、いつも先生、ここに来れば必ずスコーンを頼んでいたじゃないですか」
担当作家の何らかの変化に、吉井くんは動揺する。
「いいえ……そんな甘えた自分に卒業なの。私はこれからナップザックをしょって、水筒を常備し、そこに水道水をつめて、イギリス全土を歩かないといけないの」
気合が入っているわりに、楓子さんの目は虚ろだった。
「あのっすみませんっ、ウェイトレスさん、こちら、スコーン二人前お願いしますっ!」
吉井くんは緊急性を感じ、楓子さんお気に入りのお菓子を即、注文した。
「では、僕もナップザックをしょって水筒に水道水つめて、先生と一緒にイギリス全土を歩いて回ります! とりあえず今日のところは、スコーンを食べながら、取材の計画でも立てましょう? いえっ、もう計画なんかどうでもいいですっ、先生、少しゆっくりして下さいっ……何か……あったんですね……ううう~~」
しばらくして、吉井くんの頼んだセイロン・ウバが、ポットでテーブルに運ばれてくる頃には、楓子さんの気持ちも落ち着いていた。
*
そして五分後……。
「粉がいいわ……バターもフレッシュね。やはり、ここのスコーンはおいしいわ……。そうだわ! ねえ、吉井くん、イギリス中のスコーンをあちこちで食べながら取材をするのもいいわね。スコーンと紅茶のセットって『クリーム・ティー』っていうのよ。クリーム・ティーの看板が出ていたら、すぐそのお店に入りましょう?」
おいしいお菓子を強引にオーダーしたのがよかったのか、楓子さんがいつもの楓子さんに戻っている。
「そうそう楓子さん、ここの紅茶専門店も素敵ですけど、この先の裏通りの奥にすっごく雰囲気のいい和風喫茶があって、そこの御抹茶セットもおいしいですよーー」
吉井くんが、ちょっとテレながら話す。
「実は僕、一昨日そこで、和菓子とお抹茶を頂いたんです」
「へえ、この近くに和風喫茶なんてあったっけ? 私いつも神保町に来ると、ほぼこの紅茶専門店しか来ないから知らなかったわ」
「いや、僕も知らなかったです。この先の、裏通りの袋小路になっているどん詰まりにあったので気がつかなかったです。お店の名前なんだっけな……『松埜庵(まつのあん)』だっけ?」
「ああ、『松埜庵』ね……あそこ有名よね。確か大正時代からある老舗和菓子屋さんよ? へえ、神保町にもあったの? うちの母は『松埜庵』の豆大福がお気に入りで、よく上野の本店まで買いに行ってたわ……。あそこの豆大福は、日にちがたっても固くならないから、海外へのお土産にすごく喜ばれていたの」
「へえ、そうなんですか……僕は栗が入った水羊羹を頂きました。今度、豆大福を頼んでみようかな。お抹茶も目の前でたててくれて、その香りが素晴らしくて……お茶碗もわびさびがあって……」
吉井くんはうっとりした顔で言う。
「フフ……吉井くん、もしかしてついに例の万年筆の彼女と、お茶したのね?」
勘のいい楓子さんは、すぐに担当さんの吉報に気がつく。
「そうなんです。実は僕、一昨日、神保町の書店巡りをしてて、うちの作品の売れ行きをチェックしてたんです。あ、先生の『新宿魔法陣妖獣伝』も全巻平積みで相変わらずバンバン売れてましたよ!」
バンバン売れているのにナップザック……楓子さんの脳裏に再びまたあのしばりヒモつき簡易背負い巾着袋が甦ったが、大人の対応をしようと、すぐにそれを記憶の彼方に押しやった。
「書店を出たら、小雨の中、彼女とばったり会って、僕、びっくりして……。まだそんなに遅い時間じゃなくて、神保町の店もほとんどどこもやっていたので、まさにこの紅茶専門店にお誘いしようと思ったら、彼女が『おいしいお抹茶とか、いかがですか?』っていうから僕、その店に連れて行って頂いて……ああ、なんか緊張しちゃって、何をしゃべったのかよく覚えてないな……」
夢見る笑顔の吉井くんは、テレながらぼーっとしてしまう。
「それで、彼女……東京タワーに上りたいっていうから、今度、お連れしようと思うんです」
「わあ……東京タワー……ロマンチックね……あれ? 彼女って、東京の人じゃないの? なんかよくある観光コースね? 先日は浅草に行かれてたし……」
「いえ、東京の人だと思いますけど……」
「どこに住んでいらっしゃるの?」
「えっと、あれ……住所……聞いてないな……。この界隈のマンションかな……。このあたりって最近、どんどん素敵なマンションが建ってますよね?」
「神保町の新しいマンションに住めるなんて、かなりのステイタスよ。ねえ、もしかして既婚者じゃない?」
楓子さんは、急に心配になる。
「いや、既婚者だったら、僕に万年筆とかくれないと思うんですけど……」
「やだもう吉井くん、今は既婚者でも、もしかしてもしかすると夫婦関係が冷え切っていて、心のよりどころとなる人を、求めているっていうこともあるのよ? 優しい吉井くんの出現に、彼女の心が揺れているっていうこともない?」
「やだなあ。先生、よく僕のスマホを使って、ネットニュースなんかの男女の事件簿とか、不倫の末の愛憎劇とか、好んで読んでらっしゃるけど、そういうのはネット上の話ですから。ちょっと話を盛って書いて、読者を増やしたいだけですよ」
楓子さんはスマホを持たないので、吉井くんに会うといつも、吉井くんのスマホを借り、ネットニュースをしばし愛読する。特に男女がらみの事件が好きだ。自分のパソコンでそういう記事は検索しない。パソコンは仕事をするためのものなので、その大切な仕事道具で男女の事件簿だの、不倫の末の愛憎劇などの悲しいニュースを読むと、仕事道具に邪気が入ってしまうのではないかと恐れている。
では、吉井くんのスマホなら、邪気が入ってもオッケーなのかと突っ込めば、きっと楓子さんも返答に困るだろう。
「それに神保町のマンションに住んでいたら、旦那さんに見つかる場合だってありますから、そんな場所で堂々と僕を和風喫茶になんか誘いませんよ。しかも、彼女はいつも神保町の駅から、都営地下鉄に乗って行っちゃうので、きっと別の町に家があるんです。もしかして職場が神保町かな……?」
「あ、そっか、そうよね。神保町駅から都営地下鉄線に乗って帰って行くんだものね。私、どうしても激しい事件に結びつけるのが好きで、ごめんね……? これ、職業病よね?」
タイガーショーとして、ナイスバディの女性をたびたび登場させる楓子さんだが、こういった女性の登場とともに欠かせないのは、男女の入り組んだエログロ愛憎劇だ。
「大丈夫です! 激しい男女の事件簿、ウェルカムです! それが大河先生の原動力ですから!」
吉井くんは担当作家を鼓舞する。
「ふう……おいしい紅茶に……おいしいスコーン……。なんか私、とても幸せだわ」
その言葉どおり、楓子さんはすっかりまったりした日常を取り戻していた。
「先生、帰られる時、お好きな茶葉をあれこれ選んでいってくださいね。ダージリンとかキーマンとかオレンジペコとか……ここの茶葉、本当に一級品ですから」
「えーーそんな、いいの? じゃあ色々、頼んじゃおうかな……スコーンも持って帰りたいけど、そこまでしたらさすがに図々しいわよね……」
「スコーン、テイクアウト、ぜんぜんオッケーです! クロテッド・クリームもつけてもらえます! 好きなだけお持ち帰りください!」
これからは作家としてもっと、つつましやかな生き方をして御恩返しをしていきたいと言っていた楓子さんだが、吉井くんと話していると、ついついいつもの楓子さんに戻ってしまう。