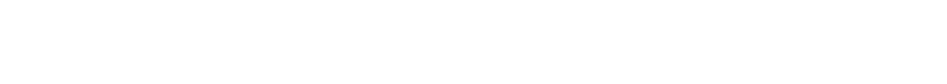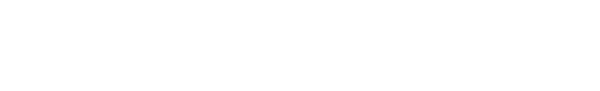WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 虹の女神』 柊坂明日子
-



第1回「神保町で会いましょう」
六月の夕暮れ時。東京は世田谷区、どの邸宅もどの邸宅も最低百坪はある昔ながらの富裕層エリアに、群を抜いて広大な土地を持つ森野楓子さんのお屋敷は、このところずっと雨に見舞われ、自慢のお庭は雑草がつやっつやに生い茂り、ジャングル化しつつあった。緑は目に優しくはあるが、暑さと湿気が苦手な楓子さんは、その有様をただただ家の中から、ため息まじりに見つめるしかできない。
「この雨が上がったら、自慢のコードレス草刈り機を持って庭に出動したいところだけど、もうダメ。だって、あたりはすでに蚊だらけだもの。雨後の筍のごとく、蚊たちも今、爆裂大量発生中ね……」
楓子さんは毎年、五月までに種まきをし、花や夏野菜を育てる。土を耕し、肥料を与え、それはもう全力でガーデニングに取り組む。しかし六月に入ると、楓子さんの行動はパタリとにぶる。外の蒸し暑さと蚊の出没が大の苦手なのだ。蚊に刺されるのがいやだったら、長袖、長ズボン、軍手、ほっかむりをしてその上にツバ広帽子で防御すればいいのだが、そこまで武装すると今度は暑くてふらついてくる。虫よけスプレーも苦手で、つけると皮膚がかぶれてくるらしい。
よって六月から楓子さんのインドア生活は始まり、それは九月あたりまで延々と続く。外出は日没後、近くのスーパーに行くくらいだ。
このアラフィフの楓子さんは、小説家だ。絵本作家としてデビューしたはずなのに、気がつくと大手出版社の翔岳館・男性読者向け小説部門「ナイト・ハンター・ノベルス」編集部の筆頭稼ぎ頭、その名も大河ショー和(短くタイガーショー)というペンネームで覆面作家として活躍している。
小説のジャンルは、SFバイオレンス・アクション・エログロ・超ハードボイルド。心はあくまでも絵本作家の楓子さんとしてはかなり不本意だが、このタイガーショーとしての印税が、世田谷区一等地の固定資産税を払ってくれている。
「でも、暑さと湿気が苦手だからって、毎年四か月近くも自宅に引きこもるって、もったいないわよね。もっとアクティブになって、人生を楽しまなきゃいけないわ。だって時間は有限だもの。そうよ、明日、雨が上がったら、まず夏野菜エリアにはびこる雑草を抜くのよ。そうでないといい野菜ができないわ。でも考えただけで億劫……やる気が出ない……。それよりもっと楽しいことがしたいわ。例えば人と会ったり、お食事したり……でも、私って極端に友達が少ないし……。よく考えるともう二週間くらい、誰ともまともにしゃべっていない気がする。最後に人に向かって言葉を発したのって、五日くらい前? スーパーのレジで『お客様、ポイントカードはございますか?』って聞かれたから『あの、今日はカード忘れちゃって』って答えて、『それでしたら、今回のレシートを次回ご提示いただけますと、その時、ポイントを加算しますね』って優しくフォローしていただいて、『ありがとうございます。すみません』って謝っただけ……。なんか寂しいわ……こんな無機質なやりとり、会話じゃないわ。こういう時こそ担当さんがいたら……一緒にワイン飲んだり、ワイン飲んだり、ワイン飲んだりできるのに……」
楓子さんは基本、一人の時はそれほどアルコールは嗜まない人だ。誰か一緒に飲んでくれる人がいて、初めて飲酒が楽しくなる。
「やだっ! ウソっ、飛んで火にいるワインだわっ! ワインよっ!」
楓子さんは、わけのわからないことを言いながら、出窓から外の様子を食い入るように見つめると、その視線の先に担当さん、現在二十八歳の吉井遼くんが、柄の長いダンディーな傘をさして、広いお庭を歩いてくる姿があった。一人暮らしの楓子さんが何事かあってはいけないと、合鍵を渡されている彼は、こうして時折、顔を見せてくれる。
担当さんは、こんな雨にもかかわらずニコニコしている。いつも機嫌のいい担当さんだが、今日はまた輪をかけてご機嫌の様子だ。
楓子さんは雨が降り込むのも気にせず、思いっきり出窓を開けると、担当さんに手を振った。
「サバ?(お元気?) 吉井くん、ソーヴィニヨン・ブランでいいかしらーーっ」
楓子さんは、お気に入りのフランスの白ワインの原料となるブドウの種類を絶叫した。
「楓子さーーーーん、チーズとサラミとドイツ・ソーセージとスモーク・サーモンと蟹コロッケ買ってきましたーーっ。蟹は本物の蟹ですっ。カニカマじゃありません!」
気が利きすぎる愛すべき担当さんは、デパ地下でゲットしてきたそれらお土産の入った紙の手提げを、高く掲げた。
*
「うわーー、先生の家、涼し~~い……ここだけ軽井沢って感じですね」
築九十年以上になる、昭和初期に建てられた、イギリス・チューダー様式の洋館のサロンに入ると、吉井くんは一瞬、ゾクッと震えた。
「え? もしかして、うち寒い? エアコン効きすぎている?」
楓子さんは、担当さんが風邪を引いてはいけないと心配になる。けれど、地球温暖化を憎む楓子さんは、どんなに暑くても、自分の家だけエアコンでキンキンに冷やして快適にするような、地球に優しくないことはしない人だ。
「あ、いえ、涼しくて気持ちいいです。外、かなりムシムシしてましたから。それに僕、背広に長袖シャツですからちょうどいいです。会社も涼しくて、上着は手放せません」
吉井くんは、いつも仕立てのいいスーツを着ている。端正な顔からは、育ちの良さがにじみでている。
「で、今日はどうして来てくれたの? 仕事じゃないわよね? 私が暑さにやられて死んでいるかどうかチェックしにきたの? 夏場は腐敗が速いものね……ありがとう」
「いえ、あの、そうじゃなくて。ほら先生、新シリーズの構想どうなりました? 『イタリア八十八ケ所闇遍路神話伝』を書くんですよね? 秋頃、イタリアに取材に行きましょうよ!」
担当さんの目はキラキラしている。
「うーん、あれねーー。私、イタリアよりイギリスに行きたいわ。ロンドンはもちろん、スコットランドのエディンバラとか、北アイルランドのベルファストとか、その新シリーズ『イギリス八十八ケ所闇遍路怪奇伝』とかに変えちゃだめ……?」
吉井くんの目は点になる。ちょっと前までご機嫌だったはずだが、今、明らかに落胆しているのがわかる。
たぶん楓子さんは、最近イギリス放送局BBCが制作した刑事ドラマかミステリーを観て、心は一気にイギリスに飛んでしまったのだと確信した。
「わかりました! 新シリーズは、イギリスを舞台にしていきましょう! なんだったら、アイルランドのダブリンまで足を延ばしたっていいです!」
作家思いの吉井くんは、気持ちをスパッと切り替えた。
「えっ、イギリスに行っていいの? うわーーどうしよう、本場のパブでビール飲んだり、ビール飲んだり、ビール飲んだり? ランチは定番のフィッシュ&チップスね? お三時にはフォートナム&メイソンで、超本格的なアフタヌーンティーとかもしちゃって? そんでもって、日曜日はやっぱり基本のローストビーフよね……って、ちょっと待って。ローストビーフなら、思い切って老舗のシンプソンズに行っちゃう? 私、清水の舞台から飛び降りるつもりでご馳走するわ!! って、そうじゃなくて! 『イタリア八十八ケ所闇遍路妖獣伝』って、結構、二人で色々とプロットを立ててたのに、吉井くん、どうしたの? こんなにあっさりイタリアを捨てて、イギリスに変えてもいいの? こういう時、吉井くんって私を説得して、当初のイタリア案を勧めるんじゃないの? それが担当さんの仕事よね?」
「先生……『妖獣伝』じゃないです。『神話伝』です。『イタリア八十八ケ所闇遍路神話伝』です。『妖獣伝』は先生の大人気シリーズ、現在八巻目になる『新宿魔法陣妖獣伝』です……」
「今そこが問題じゃないのよ? こんな簡単にイタリア案からイギリス案に変えてもオッケーなの? 私と吉井くん、二週間前ここでプロットを立てたわよね?」
「ええ……プロットを立てたといっても……先生がイタリアの高級赤ワイン、バローロを開けて、庭からバジルを摘んできて、生ハムを乗せたマルゲリータのピザを焼いて下さって、僕はタコのカルパッチョを作って……焼きナスのブルスケッタは焦がしちゃって……そういうのを食べながら『トレビの泉行って、ジェラートを食べたいわよね』とか『フィレンツェのウフィツィ美術館のカフェでカプチーノとパニーニたのみたいわーー』とか、『イタリアってアモーレ(愛)の国だから、こんなしょうもない私だけどナンパされたらどうしよう。そういう時は、ワタシこう見えて独身、シングル……グラッツィエ、バット ノー(ありがとう、でもダメ)って言えばいいかしら……?』とか、英語まじりのイタリア語をならべて、あれはまったくプロットじゃなかったような。ですから、先生が元々お好きでしたイギリスが舞台でもゼンゼン構いませんよ」
楓子さんにとことん甘い担当さんは、またニコニコの笑顔で方針転換をしてくれる。
「吉井くん、優しいのね……っていうか吉井くん、もしかして何かいいことがあったの? 春に四国でこんぴらさんと弘法大師空海生誕の地である善通寺にお詣りして、プラス、瀬戸内海のご先祖様のお墓参りをしてから、運気爆上げしてない?」
するどい楓子さんは、吉井くんにたずねる。
「あっ、そういえばそうですね……そうそう、すられたと思った財布は、ずいぶん日にちが経ってからですけど、中身まったくそのままで交番に届けられていましたし、小火を起こされた自宅マンションは、三か月賃貸料が無料になりましたし、あとそれと……僕、この間、素敵な人に出逢ったっていうか……」
吉井くんはここでちょっと顔を赤くする。
「えっ、もしかして吉井くん、恋人できた宣言? それ、もっと早く言ってよ!」
「あ、いえ、恋人じゃないですよ。僕なんてすぐフラれちゃうから、ダメですよ」
「フラれないわよ。吉井くんの良さは、この私が一番よく知ってるから! やっと春が来たのね?」
「いえ、ダメです。ほら、最後にお付き合いしてた人、翔岳館の同期の女性だったんですけど、その彼女、僕が担当していた作家さんと、いきなり結婚しちゃったじゃないですか」
二年近く前のことを、吉井くんはまだ引きずっている。
「ああ……あの彼女ね……吉井くんが担当していた作家の先生のご自宅に招かれた時、吉井くん、彼女も連れていっちゃったのよね? そしたら、その作家さんと彼女が意気投合して……地獄絵図だったわね……」
「ええ……彼女は、元々その先生の作品のファンで、一度会ってみたいっていうから一緒に連れていって、で、その先生は彼女より三十二歳も年上だから、恋愛対象にはならないって思ってたんですけど……」
吉井くんは深いため息をつく。まだ傷は癒えていない。
「吉井くん、それでよかったのよ! だってもし、吉井くんがその彼女と結婚して、その後、ご夫妻でその先生の家に招かれて、そこで吉井くんの奥さんとその先生が恋に落ちたら目も当てられないわよ? 修羅場だからね? 立ち直れないわよ? 死人でるわね?」
「あっ、ホントそうですよねっ!? くっつく人は、どうしたってくっつきますから! 僕、傷が浅めに済んでよかったのかもしれません!!」
「そうよ、その彼女とは縁がなかったのよ。彼女が今幸せならいいじゃない? 幸せのきっかけを作ってあげた吉井くんには、絶対神様からのご褒美があるから」
楓子さんは、必死で吉井くんを慰める。
「で、今また、ステキな出逢いがあったのよね? なんか、今日の吉井くんからは幸せオーラが出てるから、わかるわ!」
「いえ、そんなんじゃないです。二週間くらい前かな……会社帰りの地下鉄神保町駅で、着物の女性が困ってて……なんか、パスモとかスイカのカードを持ってなくて、自動券売機で切符を買いたいようなんですけど、何度入れても百円硬貨が戻ってきてしまって、で、よく見たら百円は百円なんですけど、その百円硬貨って裏が稲の柄で、ちょっと古い昭和のものなので、もう機械が受け付けてくれないんです」
「やだ懐かしい。稲の柄の百円銀貨……私もまだ持ってるわよ、昭和の記念なの」
昭和好きの楓子さんは、目を細めてニコッとする。
「で、僕、自分の硬貨を使って切符を買ってあげたんです。彼女、浅草に行きたいっていうから……」
「吉井くん、優しいわね……で、そこでなんか進展があったのね?」
「あ、いえ……彼女、自分が持ってるその稲の百円硬貨を僕に渡そうとするから、大丈夫です、それ、きっと価値がありますよ、持っていると良いですよって、僕は受け取らなかったんです……」
「どんな方? 可愛い感じの人?」
「そうですね……可愛くて、美人でした。透け感のある藤色の絽の着物がよく似合ってて。スラっとした感じで、笑うと優しい雰囲気になって……上品でした。もしかして、神保町界隈でお茶とかお花を習っているのかも……」
「絽の着物なんてお洒落ね……年はおいくつぐらい?」
「僕と同じくらいか、ちょっと上かな……いや、下か……? うーーん、何だかよくわからないな……」
「で、吉井くん、どうしたの? お茶にお誘いしたの?」
「ああ……いえ……僕……そこまでグイグイいけなくて……だって、彼女、浅草行く用事があるから……」
「なんでっ? グイグイいっていいのよ、そこ、グイグイいくところよ? で、券売機の前でさよならして、おしまい?」
「え……だって、その日、僕、先生の家に行くところだったから。ほら、『イタリア八十八ヶ所闇遍路神話伝』のプロット作りに、二週間前、僕、ここへ来たじゃないですか?」
「吉井くん、私のことはどうでもいいの! こういう時は、自分の幸せを優先してちょうだい……」
楓子さんは涙目で、担当さんに訴える。
「あああ……でも大丈夫です、僕、その後また、彼女に会うことができたんです」
「えっ、そうなの!? よかったわ……。で、どういう展開になったの?」
「出逢って一週間後、また彼女が、例の都営地下鉄の券売機の前にいたんです。彼女、僕のことを待っていたんです。先日はありがとうございましたって、また別の涼やかなお着物で現れて……なんと僕に、この間のお礼にって万年筆を下さったんです」
「えーー、それ、すごくない? もう完全に両想いよね?」
「いえ、それはどうかな……。『あなたは、このあたりのどこかにお勤めでしょうから、きっと書き物をなさると思って』って、万年筆を渡してくれて……」
「吉井くんが働く神保町駅界隈は、出版社だらけってことをご存じだったのね……で、万年筆をお礼に下さるなんて、粋よね……?」
楓子さんは、その女性に感心してしまう。
「で、吉井くんは万年筆のお礼に、お茶とかにお誘いしたのね?」
「それがですね、僕、その日は校了とかでめちゃくちゃ忙しくて、駅に行った時はもう十一時を過ぎてましたから、もうどこもお店は閉まっていて……」
「え……お誘いしなかったの……?」
「いえ、お誘いしました。今日はもう時間が遅いですから、今度、お食事でもいかがですか? って聞いたら、じゃあまたその時にね、って彼女、そのまま都営地下鉄の改札に入っちゃって、エスカレーターに乗って、ス――って下がっていっちゃって……僕、都営地下鉄じゃなくて半蔵門線だから……追いかけられなくて……」
「ええー、なんで一緒に行かなかったの?」
「ホントそうですよね……僕、どうしてこうチャンスをものにできない男なのか、ほとほと嫌になっちゃって……お名前もうかがってないし……いや、もっとよく考えると、あんな高価な万年筆をすんなり受け取って、そのまま別れる僕もどうかしているし……いや、はっきり言って浅草までの切符代のお礼に、あの万年筆はどう考えたってつりあわないし遠慮するべきなのに……気がついたら握ってて……」
吉井くんがあまりにもがっくりするので、楓子さんはもうこれ以上彼を責められなくなった。
「大丈夫よ吉井くん、きっとまた彼女に会えるわ。だって彼女、吉井くんにお礼をしたくて、わざわざ夜の十一時過ぎまで駅で待っていてくれた人よ? 素敵な万年筆も下さったのよね?」
楓子さんは、吉井くんを励ました。
「そうなんです。黒のうるしの蒔絵の万年筆で……菖蒲の花の柄で……すごく書きやすいんです……あ、今、お見せしますね」
そう言って、吉井くんは背広の胸ポケットを探るが――。
「あれ……ない……あ、そうか……今日、仕事をしてて使ってたんだ……。会社の引き出しに入れてきちゃったか……」
「素敵ね~~、着物に万年筆ね……。私の好きな昭和の世界だわ……」
「なんか、そういえば、楓子さんみたいな雰囲気の人でしたよ。ほら、楓子さん、時々着物きてらっしゃるし、おっとりした感じで……優しいし……」
「そうなの? また会えるといいわね。今度会ったら、夜の十二時でもタクシーに乗って、行けるとこまで行くのよ。六本木とかだったら、ステキなバーとか開いてるわよ。ホテルのラウンジもやってるしね」
「えーーそんな、いきなりホテルとか、行けませんよ~~」
吉井くんは赤くなって言う。
「やだっ、ホテルのラウンジよ、ラウンジ! 深夜まで営業してるから、お茶のんだり、シャンパン飲んだり、お洒落な軽食頼んだりできるから!」
「あっ、そ、そうですね……ラウンジ……ラウンジ……ラウンジ……」
吉井くんはテレ笑いをする。
気づくと雨は本降りになっていた。日の出から日の入りまでの時間が一番長い夏至を過ぎたばかりで、しかも六時前にもかかわらず、すでに外は薄暗い。
遠くの空では、時折閃光が走りゴロゴロ鳴って、いよいよ雲行きはあやしくなっていく。
「では、ソーヴィニヨン・ブランで暑気払いしましょう? 吉井くん、いつも色々お土産を持ってきてくれて、ありがとう。吉井くんを彼氏にする人はきっと、幸せになるわね」
楓子さんは、いつだって担当さんの幸せを心から祈っている。
けれどつい、次の瞬間、小さくため息をもらしてしまった。
「え? ど、どうしたんですか……楓子さん、なんか元気ないですよね?」
吉井くんはサロンの隣にある食器庫に入り、ウォルナットの戸棚から、アフタヌーンティー用三段重ね、銀のケーキ・スタンドを持ってくると、そこに自分の持ってきたチーズ、サラミ、ドイツ・ソーセージ、スモーク・サーモン、蟹コロッケを美しくセッティングしながら、担当作家の憂鬱に気がついていた。
楓子さんは、しょんぼりしながら、白ワインのコルクをキコキコ開けている。
「吉井くん、春の5Kって知ってる……?」
「ええ、知ってます、前に先生、教えてくれましたよね? 花粉、強風、乾燥、寒暖差、黄砂。この五つがそろうと注意なんですよね」
「今、私、夏の5Kなの」
楓子さんは、唇をかみしめて言う。
「夏の5Kは……知りませんけど……どうしたんですか……?」
「夏の5Kはね……①蚊が大発生、②固定資産税の納期、だけじゃない、世田谷の③区民税の納期もあり、④経済的に追いつめられ、⑤怪奇現象もおこる」
破格の固定資産税を六月に一括で払った後の楓子さんは、毎年いつも抜け殻のようになる。実は今日はその抜け殻の日だった。
「固定資産税もすごいけど、区民税もなかなか手ごわいの。でも私、頑張った……」
楓子さんは、基本ものすごい家のお嬢様だった。お祖父さまは貿易会社を興し一財産を築き、今のこの世田谷に広大な土地を求め、それはもう当時としてはびっくりするような豪華な洋風のお屋敷を建てた人だ。昭和の初期、政府の要人が海外からいらした時は、森野家を借りての盛大な晩餐会がしょっちゅう開かれていた。
そして楓子さんのお父様といえば、ヨーロッパやアメリカの領事や大使を歴任した優秀な外交官だ。楓子さん自身もフランスやイギリス、そしてアメリカでの生活を体験している。
そのお祖父様、お父様がご存命の頃は、お屋敷にはお手伝いさんや庭師さんや御用聞きさんが大勢出入りしていて、賑やかかつ優雅な日々だったのだが、今、一人残された楓子さんは、庭師も自分、お手伝いさんも自分、御用もすべて自分で聞いて何とかする。そして、このとんでもなく固定資産税の高い土地を維持するために、日々戦っている。どれだけの敷地があるかというと、屋敷の玄関で靴を履いて、それから正門までたどり着くのに、庭の雑草をかき分け、ごちゃごちゃ歩いて三分近くかかるといったら、想像できるだろうか。
「私、税金を分割で払うのがダメなの。一気に全額払わないと、納期ごとに追いつめられるような気になっちゃって……で、今朝ちょうど固定資産税と区民税を一気に払ってきたところ……。でもよく考えると、それが払えるってことは、お仕事を下さる翔岳館さんと、常にサポートしてくれる吉井くんあってのことだからホント感謝だわ……吉井くん……そして翔岳館さん……ありがとう……」
楓子さんは頭を下げ、しみじみとお礼を言う。
「いえ、僕なんて、たいした力になっていません、先生が頑張った結果です! あの、それより怪奇現象って、どういうことですか……?」
心霊現象やスピリチュアル系に弱い吉井くんは、先生の今年の税金完済感動秘話より、そこが何よりも気になっている。
「あら、言ってなかった? うち、夏はお盆近くになると、お祖父ちゃまとかお祖母ちゃまとか、お父さんはあまり出てこないけど、お母さんはたまーーに来るわね……身内だからあまり怖くないけど」
「え、見えるんですか……?」
吉井くんの顔が引きつる。
「見えるっていうか……猫が教えてくれるの。来てるよ、って。東京のお盆は七月中旬だから、七月に入るあたりから、うちの猫たちが突然、何もないところをじっと見つめて、にゃあにゃあ鳴いたりね……」
楓子さんの言葉に反応するように、二階では、飼い猫のシンプキンと松田さんとルルちゃんが追いかけっこを始め、ドタバタ大騒ぎしている。
「猫ちゃんだけじゃなくてね、外出先でなんとなくふらりとリカー・ショップに入ったら、そこの店主のおじいちゃまが、この日本酒はおいしいよ、最高級だけどお勧めだからって、私はただ、ベルギーのビールが欲しくて買いに寄っただけなのに、いきなりそう言われて、で、勧められたその日本酒を見ると、それが普通だとなかなか手に入らない、お祖父ちゃまの大好きだった銘柄のお酒だったり……。あと、知らない町の老舗の和菓子屋さんの前を通った時、いきなりそこの店主のおばあちゃまが出てきて『今日はアジサイのねりきりがあるから、どう?』って声をかけてくれて、店をのぞくと、うちのお祖母ちゃまのいかにも好きそうな和菓子があったの。お祖母ちゃま、季節ごとのお花の形のねりきりが大好物で……とにかく、そういうお酒とか和菓子を買ってお仏壇にお供えすると、しばらくするとどこからともなくチーーンって、お鈴の音が聞こえてくるのよ。ありがとうってことみたい」
「あうあう……別に形として表れるわけじゃないんですね……でも、仏壇からチーンって聞こえてくるって、かなり怖いかも……僕ダメだ、そういうの」
吉井くんは、まだビビッている。
「音といえばピアノはよく鳴るわね……。たぶん、母が弾いているのだと思うけど、夜中にシューマンの『トロイメライ』が聞こえてくるの……。七月から八月にかけてが多いわね。うちの母がよく弾いてくれた曲でね。で翌朝、ピアノの蓋を開けてみると、鍵盤の上にかけてあるフエルトの布のカバーがちょっとずれていたりして、私が弾いたのよって、言いたいみたい……」
「ああ……それはかなり……背筋が凍る……案件だ……」
「平気よ。だって自分の母親だもの……トロイメライを聴くと、ああ大丈夫だわ、私……一人じゃないんだって思うの。でも、八月のお盆が終わってしまうとパタリと誰も来なくなってしまうから、すごく寂しいわ……お庭で送り火をすると、スーーーーッっとみんなが帰っていくのが、よくわかるの……家の中があっという間に空っぽになる感じ……」
楓子さんは、遠くをぼんやりと見つめる。
「わかりました。じゃあ僕、八月のお盆の後は、先生が寂しくないようにもっと頻繁にここに来て、一緒にプロット立てたり、プロット立てたり、プロット立てたりしますね」
「プロットばかりなのね……」
「あ、違います、えっと、何かものすごくおいしいワインのおつまみとかも、持参しますので…それとあの、先生は一人じゃないですから。僕がいつも一緒ですからっ。合鍵も持ってますから、すぐ駆けつけます!」
この若い担当さんは本当に優しい。
「ありがとう、吉井くん……でも今年の夏は、そうはいかないわよ……」
「どうしてですか?」
「あなたは久々の彼女ができて、それどころじゃなくなるのよ。いい? することはいっぱいよ? 七月は、浅草寺のほおずき市に行ったり、入谷の朝顔まつりに行ったり、とんとん拍子に話が進めば、八月は彼女を連れて四国のご実家へ帰るのもアリよ。ここは短期戦で恋を成就させてほしいの!」
「先生……そんなドリームみたいな話……やめて……」
「いえ、吉井くん、あなたはもう次のステップへと進まないとだめよ。いつまでも私とここでワイン飲んだり、シャンパン飲んだり、ビール飲んだりしている場合じゃないの。今は、着物の彼女と全力でおつきあいをする時なのよ! チャンスの神様は前髪しかないの! チャンスの神様がやって来たと思ったら、すぐにその前髪をつかまないと!」
担当さんの幸せを祈り、楓子さんは熱く語った。
「先生、ありがとうございます。じゃあ僕……今回はちょっと頑張ってみます。では、とりあえず、この冷えたソーヴィニヨン・ブランで乾杯しましょう?」
と言ったとたんに、
バリバリバリバリ……ドカーーーーン!!
すぐ近所で、かなり大きな落雷があった。いや、もしかして楓子さんの家の敷地内に落ちたのでは? と思うほどの爆音だった。
と同時に、あたりは真っ暗になり、停電となる。
とたんに、二階で遊んでいたはずのアメショー柄のシンプキンと、トラ柄の松田さんと、一番チビっこの白猫ルルちゃんが、猛ダッシュで一階のサロンに集合していた。
吉井くんは腰を抜かし、ソファの後ろで身を伏せている。
「みんな、大丈夫よ、ただの雷だからね……こわくないのよ。一緒にゴハンを食べましょう?」
楓子さんは、猫たちと担当さんを落ち着かせると、あちこちのキャンドルに火を灯し、いつものマホガニーの円テーブルに着席した。そして、何事もなかったかのようにグラスにワインを注ぐ。一人暮らしが長いと、落雷や停電くらいで騒いだりはしない。地震も震度5弱くらいまでなら、そこそこ落ち着いている。
そして吉井くんはようやく落ち着きを取り戻し、テーブルにつくと、シンプキンはすぐその吉井くんの膝の上に乗る。ルルちゃんは楓子さんの膝の上。松田さんは、テーブルの端でカリカリを食べ始める。何とも長閑なディナーだ。
その時、ふわりといい香りがサロンに広がった。
「あれ……先生、今日、香水つけてます?」
吉井くんが気づいた。
「視覚が悪いと、嗅覚が冴えるものね。ホント、何かいい香りがするわよね? 私は香水つけてないけど……スミレ……かな?」
楓子さんも考える。
「ちょっと石鹸っぽい香りもしますね……?」
「ウッディな香りもするから……スミレじゃないわよね……」
「うーーん、なんでしょう……でも、なんか落ち着くいい香りです……まさか、猫ちゃんのカリカリじゃないですよね?」
そう言って、吉井くんはシンプキンにあげているドライ・フードをつまんで匂いをかいでみる。チキンとターキーの匂いだ。
「不思議ね……窓、開けてないんだけど……どこからそんな匂いが入り込んでくるのかしら……。でも、停電も悪くないわね。五感が研ぎ澄まされて、非日常が楽しめるわ」
キャンドルライトでのディナーは、意外にも盛り上がり楽しかった。そして不思議な花の香りはいつのまにか、チーズ、サラミ、ソーセージ、スモークサーモン、蟹コロッケの香りにとってかわられ消えていた。