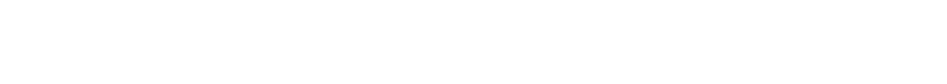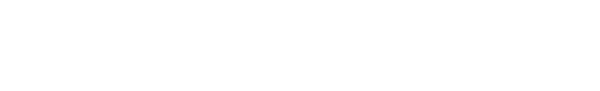WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 瀬戸内海の秘密』 柊坂明日子
-



第2回「春爛漫、運気上げ上げツアー」
翌日、朝早い東京駅の東海道新幹線下りホームに、発車のベルが鳴っていた。
「吉井くん、これ『のぞみ』よ。博多行きだから、取り敢えず乗っちゃいましょう?」
楓子さんは、キャメル色のカシミアのオーバーに、かなり大きめのヴィトンの巾着型縦長リュックを背負っていた。
「今日は平日だし、時間も早いから、きっとがらがらよ。一号車から三号車までが自由席ね。浮いた指定席料金代で、お弁当とかおつまみを豪華にできるわ」
楓子さんはそう言うと、さあ、これからいい仕事をする、とばかりに、張り切った姿で発車の時を待っているのぞみに乗り込んだ。
吉井くんもそれに続くと、ほどなくしてプシューッとドアが閉まる。
二人は自由席を目指し、車両をズンズン移動していくと、とんでもない光景が嫌でも目に入ってくる。なんと指定席はどこもぎっしりだ。関西に行く出張のビジネスマンと、子供連れの家族がなんだか多い。あと大学生風の友達同士、などなど。
「なんで、平日の早朝からこんなに混んでいるんでしょうね。しかも、始発駅なのに。指定席がこんなに満席だったら、どう考えても自由席はもっと混んでますよね」
吉井くんは今、不安しかなかった。
「大丈夫よ、こういう時は逆に自由席が空いたりしてるものよ。日本の方々って、みんな心配性だから、とりあえず指定席をとっておかないと、落ち着かないだけ」
「あ……でも、ほら僕、今、運気サイアクだから、悪い予感しかしないです……あ、そうか、今は春休みなんだ! しかも金曜日。親は金曜日に有休をとって、子供を連れて、金土日と旅行に行くんだ! 大学生たちは卒業旅行か! 混んでいるわけだっ」
それに気づいた吉井くんは、楓子さんを押しのけると、一歩前へ出た。
「先生は、ゆっくり来てください。僕、先に自由席の様子を見てきますっ」
二十八歳の青年は、担当作家を置いて小走りで先を急ぐと、あっという間に遠くの車両に消えていった。
それからしばらくして、楓子さんがようやく三号車手前の連結部分にたどり着くと、そこにはひきつった顔の吉井くんが、唇を震わせて、呆然と立ち尽くしていた。吉井くんの肩越しに自由席の様子を見ると、そこは見事に満席だった。
「だ、大丈夫ですヨ……先生……ほら、ここは大船に乗った気分でいて下さい……翔岳館が先生にグリーン車をご、ご用意いたしますから……」
「だ、だめよ、私、グリーン車なんて乗れないわよ。そこまでされたら、本当に新シリーズを書かなきゃいけなくなるじゃない。私、ただ気晴らしに四国に行ってみたかっただけだから……本物の讃岐うどんとか、食べたかったし……」
「えっ、ウソっ、新シリーズ書くっていうから、僕、今日は出張あつかいで、帰郷できるようになったんですよっ」
「吉井くん、そんなことを言っているうちに、もうすぐ品川よ、どうしよう、もっと人が乗ってくるわっ」
楓子さんは、電車内で長時間立っているのがダメな人だ。フツーの電車でもシートに十五センチほどの隙間があったら、そこにうまいことグイグイくい込んで座ってしまう技術を持っている。昔、お嬢さまだった頃、小学校から大学まで、お抱え運転手つきの車で登校していたため、混雑に弱い。
「わ、わかりましたっ、グリーン車は僕がジバラ切ります! 新シリーズの事は取りあえず横に置いといて、今はまず席を確保しましょう! 僕、先生を岡山まで立たせるわけにはいきませんっ」
優しい吉井くんは、楓子さんのヴィトンの特大リュックを背中から外すと、それを自分の肩にかけ、ものすごい勢いで、こんどはグリーン車へ向かい始めた。結局さっき乗り込んだあたりの車両に舞い戻る形だ。せめて担当作家の荷物を背負って、その先生の体力の消耗を最小限にしたいと、吉井くんは必死だ。
シュワワワ~~~~。
自動ドアが開き、グリーン車に一歩足を踏み入れると、そこは別世界だった。
「よかったーー。席が空いてる~~。しかもなんか、すごくいい匂いがする~~」
通路は広々、高級シートはゆったり、グリーン車内を見渡すと、品のいいアラカン・マダム、また品のいいアラカン・マダム、そしてまた品のいいアラカン・マダム……。シートを向かい合わせにした、四人のセレブ・グループ、あるいは通路を挟んで左右四人プラス四人を対面させて盛り上がっている八人のセレブ・グループ、そんなゴージャスな女性のかたまりがあちこちに発生している。その合間、合間に空席がある。この車両は半分も席が埋まっていない。六十八人乗れるグリーン車両なのに。
「楓子さん、取り敢えず、座りましょう。車掌さんが来たら、グリーン料金を払えばいいだけですから。ここは僕に任せて下さい」
吉井くんが、楓子さんのヴィトンのリュックを網棚に乗せると、斜め横のグループの美しいおばさま方の声が聞こえてきた。
「あれ、『ランドネ』ね? もう廃盤だけど、綺麗に使ってらっしゃるわ。私、ランドネ好きだったわーー。お洒落よねえ、若い方が旅行にランドネって、いいわね。パリの街角を思い出すわ~~」
「あの……楓子さん、ランドネってなんですか?」
吉井くんは小声で楓子さんに聞く。
「シャネル五番、十九番、ディオリッシモ、ミス・ディオール、レールデュタン、ゲランのミツコ……」
楓子さんが目を閉じてブツブツ呟いていた。
「楓子さん、ミツコって誰?」
「あ、香水よ。ここにいるマダムたちの香水のかおりをかいでいたの。みんな昭和三十年代前半に生まれたセレブたちね……素敵……シャネルとディオールとニナリッチとゲランが混ざり合っても、その甘くて優しい本物の香りは決して互いを否定しないの……」
「えっ、今、そこですか? そうじゃなくて……ランドネ……」
「そこよ。このグリーン車にいるマダムたちは、離れ離れに座っていながら、実は一つのグループなの。彼女らの洋服のコンセプト、バッグの選び方、履いている靴を見れば一目瞭然ね。もしかして、この車両、春のクラス会の旅行とかかしら……?」
探偵業を趣味とする楓子さんは、いきなりミス・メープルに変身して、車両内に集う人々をウォッチしていた。
と、その時、楓子さんの前の席に一人でかけているふくよかな体型の年配女性が、通路に出てくると、楓子さんと吉井くんの横に立ち、申し訳なさそうに頭を下げた。
「あの、実は、このグリーン車は、私どもがすべてツアーで借り切っておりまして」
彼女の手には、小旗が握られていた。パタパタと振ってみせる。
なんと小旗には、『ミステリー・ツアー 白薔薇女学院御一行様』と書かれていた。彼女は添乗員さんだ。大手旅行代理店の紺のスーツを着て、胸には社員バッジをつけていた。よく見ると、グリーン車の扉にも『ミステリー・ツアー催行中』と、張り紙がはられている。そんなことにはまったく気がつかなかった二人だ。
「そ、そうだったんですかっ、すみません、そうとは知らず……。自由席も指定席も満席だったもので、僕ら、ここなら大丈夫だと思って。とんだお邪魔をしましたっ」
吉井くんは、謝り、楓子さんのヴィトンのリュックを網棚から降ろすと、肩にかけた。また、どこかに移動だ。
一方、楓子さんは、ほんのちょっと前、ポケットから『都こんぶ』を取り出し、一枚口に入れたところだ。
「せっかくの雰囲気を台無しにしてしまって、ごめんなさい……きっと、この先、新横浜とかからも、お仲間が乗り込んでいらっしゃるのね……?」
しょんぼり謝る楓子さんの口から、昆布がピラピラ出たり入ったりしているのが見える。
「まあ、それ『都こんぶ』ね? 懐かしいわ。まだ売っているの?」
楓子さんが握っている『都こんぶ』の赤いパッケージを見ると、いきなり添乗員さんが和んでしまう。
「あの、よろしかったらどうぞ、皆さんで召し上がって下さい。たくさん、持ってきたので」
楓子さんは、吉井くんが肩にかけたヴィトンのリュックに手をつっこみ、そこから封の切ってない『都こんぶ』を二、三箱つかむと、添乗員さんに渡した。
「あ、いえ、私、そういうつもりじゃ……。え? いいの、こんなに頂いちゃって?」
「いいんです。遠足に『都こんぶ』は絶対ですから」
楓子さんが言うと、斜め横の別のシートの女性が立ち上がって言った。
「添乗員さん、そこ、お二人に座っていただいたらよろしいじゃない? どうせこんなに空いているんだし。しかも、爽やかなイケメンがこんなにカッコよく『ランドネ』を持っているっていうのが、目の保養になるしね?」
また、ランドネだ、と吉井くんは思った。
その彼女は、スラっと背が高く、黒のカシミアのワンピースをストンと着こなし、首回りに同じく黒いミンクのマフラーをしている。髪は金のメッシュを入れたベリーショート。爪のネイルは黒の衣装に対抗するように華やかで、すべてに違うビジューがほどこされ、そのお洒落さに、誰もが目を奪われる。すると彼女の周りの対面シートの七人が、パチパチと手を叩いていた。あなたたち、座ってていいのよ、ということらしい。素敵マダムのおばさまたちは、優しい。
「それではあの……元女学生、今アラカンのミステリー・ツアーではございますが、もし、居心地悪くありませんでしたら、そのままおかけになって、私たちと一緒に旅を楽しんでいただけます?」
大手旅行代理店の年配添乗員さんは、にこっと笑って、グリーン席を提供してくれた。
「ありがとうございます! あの、では僕ら、ここの席料をお支払いしますね!」
吉井くんが財布を取り出して言った。この間すられたので、新しい財布を持っている。
「いいのよ、ここ全部貸し切りだから。今さら関係ないの。おばさんたちは、イケメンと『都こんぶ』を持っているお嬢さんに弱いのよ」
添乗員さんが言った。
楓子さんは今、自分がお嬢さん扱いされたことに衝撃をうけている。そんな扱いは何十年ぶりだろう。
「あの、でも、皆さん、どちらまで行かれるんですか? 僕たち岡山ですけど……」
吉井くんが言うと、添乗員さんの目がキラっと光った。
「あ、そっか、ミステリー・ツアーだから、行先は言えないですよね?」
吉井くんは、すぐに察して、フフッと笑った。
楓子さんは、面白そうなツアーに巻き込まれ、わくわくしている。
そして二人は周りのおばさま方にお礼を言い、改めて着席すると、
「はい、吉井くんもどうぞ」
と、楓子さんは、担当さんにも赤い箱を差し出した。
「それってガムじゃなかったんですね……こんぶかあ……でもなんでこんぶ?」
「吉井くん、昭和の遠足っていったら、みんなこれを持ってきていたのよ。バスとかで長時間揺られても、『都こんぶ』さえあったら、酔わないし、気分爽快なの」
このようにアラフィフの楓子さんは、昭和が大好きだ。令和になった今でも、昭和の生活を維持している。ゆえに、令和三年は、楓子さんの中では昭和九十六年、令和四年は昭和九十七年の計算となっている。あと三年経ったら、自宅でひっそりと昭和百年祭をやるらしい。
それだけではない。楓子さんは富裕層なのに、今でもあの昭和の頃に活躍した三菱の巨大ブラウン管カラーテレビを、家族のように愛おしんでいる。かなり映りが悪くなっているが気にしない。そして、どんなに吉井くんが勧めても、プレゼントすると言っても、画像のいい薄型デジタル・テレビを家に置こうとはしない。薄型テレビを手に入れたとたんに、今あるその三菱巨大ブラウン管テレビが気落ちして、自分の役目は終わったとばかりに壊れてしまうと信じているのだ。
実際、楓子さんにはヘンな力があって、新しい洗濯機や冷蔵庫が欲しいと思っただけで、家にある古いそれらが、いきなり動かなくなってしまったりすることは一回や二回じゃない。楓子さんいわく、物にも心があるそうだ。
そして楓子さんにとって、NTTは電電公社、JTは専売公社、JRは国鉄、財務省は大蔵省。防衛省はいまだに防衛庁。ちなみに現在の総理大臣は佐藤栄作さんあたりで止まっている。そして、都知事は美濃部さんだ。
小池百合子さんに関しては、日テレ系の大人気ワイドショー『ルックルックこんにちは』で、竹村健一先生の『世相講談』でアシスタントとして活躍していたアラブ研究家の小池ユリ子(当時の表記)お姉さんの記憶しかない。
ドイツは今でも東と西に別れ、チェコスロバキアもまだ分断してない。ロシアは当然、ソビエトだ。
『都こんぶ』以外の食品に関して言えば、グリコのプリッツは、初期に売っていた基本のロースト・プリッツをこよなく愛している。くわえて『森永ハイチュウ』は、その前身だった[食べられるガム]というキャッチコピーの『森永チューレット』の名前で呼んでいる。昭和の事を考えると、脳内にドーパミンがあふれるらしく、吉井くんも楓子さんの昭和好きを止めることはできない。
「あ、では、一枚頂戴しますね」
吉井くんは楓子さんの差し出したこんぶの赤い箱から、一見チューインガムのような白い粉をふいたこんぶを取り出し、口に入れた。
「ああ……こんぶだ……こんぶ以外の何物でもない……甘くてちょっと酸っぱい、でも、なんか、気分いい……っていうか、奥深い味ですね……っていうか、おいしい!」
吉井くん、昭和の味の洗礼を受け、今、気分があがっている。
「あの、それより先生、ランドネって、なんですか……」
さっきからどうも引っ掛かっていることを、楓子さんに聞く。
「私の持ってきたヴィトンのリュックの名前よ。フランス語でrandonneeっていうの。ランドネって言うのは、遠出って言う意味よ。遠足みたいなもの」
「わあ、先生、さすがです、さすがトリリンガル、じゃなくてクワドリンガルです」
「昔とても流行ったの。父にミラノで買ってもらって……。でも、その父ももういなくて、私、あのランドネを見ると、楽しかった父とのイタリア旅行を思い出しちゃうから、長い事使えなくて、でも、今日は久しぶりの遠足だから、背負ってきちゃったわ」
「わ~~、先生の哀しみって、なんか壮大でいいですね。フランスの鞄をイタリアで買うんだ~~。いーなー。うらやまー」
吉井くんはうっとりしている。
と、その時、楓子さんの席の三列前の女性が一人、席を立つと、洗面所に向かうのか、通路を歩いてきた。
小柄でものすごく痩せていて、でも、誰もが二度見したくなるほどの美人さんだ。アラカンでも美人は美人だ。肩までの巻き髪が優しい雰囲気で、クリーム色のシャネル・スーツがよく似合っている。
薬指には、大きなダイヤの指輪に金の結婚指輪をあわせている。とてもいいところの奥様というのがよくわかる。ところが、その彼女がシート脇についている荷物かけのフックに、うっかり自分のバッグのひもを引っかけてしまい……。
大きくよろけて通路に倒れそうになった瞬間、吉井くんがサッと飛び出し、彼女の肩と腕を支えると、事なきを得る……。
「まあ、どうしましょう……ありがとう……。みっともないわね、私……。ホント、ドジで……申し訳ないわ……ごめんね、ありがとう」
小柄美人の奥様は、消え入りそうな声で吉井くんにお礼を言う。
「いえ、大丈夫でしたか? 脚、捻挫とかされていません?」
吉井くんはそれより、彼女があまりにも痩せていて、支えた体が羽のように軽かったことにびっくりしていた。
「大丈夫よ、本当にありがとう、助かりました」
小柄マダムはまた深々と吉井くんに頭を下げた。美しいが、頼りなげな人だった。
その人は、車両を出ると、洗面所へと向っていた。
「さすが吉井くんね。だから私、いつも吉井くんといると安心なの。吉井くんはいつだって私の自慢よ」
楓子さんは、改めて自分の担当さんに感心する。
「あの……大河先生、そんなに褒めてくれるのでしたら、新シリーズを書きましょうよ。『四国八十八ケ所闇遍路魔界伝』とか……。霊場ごとに魔物が出てきて、巡礼途中の……昔、散々非道なことをしてきた政治家とか、パワハラ・モラハラし放題だった極悪サラリーマンとかに、魔物が取り憑いていくんです。それを主人公が斬るっていうカンジでどうでしょう?」
「あっ、新横浜駅よ! 吉井くん、ちょっとごめんね、私、崎陽軒のシウマイ買ってくる!」
「えっ、先生、やめてっ、そんな時間ないですっ! あーーーーっ!」
止める吉井くんを振り払い、楓子さんは、あっという間にホームに出ると、近くのキオスクへと走った。吉井くんは、連結部分の扉の前で立ち尽くし、今か今かと手に汗握り、担当作家が戻って来るのを待っていた。
そして、発車のベルが鳴り響きだす……ああ……もうダメ、と吉井くんが頭を抱えたところで、楓子さんが満面の笑みで、崎陽軒のシウマイを抱きしめ、飛び乗ってきた。
「先生……僕、もういやだ……どうしてそんな無茶ばかり……乗り遅れたらどうするんですか……先生、スマホ持ってないし……連絡取れないし……体に悪い……」
泣きそうな吉井くんの小言はスルーして、楓子さんはさっさと席に戻ると、網棚のランドネを下ろし、そこから赤ワインを一本、取り出した。ついでに、透明プラスチックのワイングラスまで二個、テーブルに並べる。
「そんなものまで……持ってきたんですか……道理で……ガシャガシャいってた……ガシャガシャ……ガシャガシャ……」
「だって、旅はやっぱり、楽しくなくちゃ」
と言った後に、楓子さんは「あっ!!」と叫ぶと顔面蒼白になった。
「先生、どうしましたっ……」
「ワ、ワイン・オープナー……忘れたっ……」
楓子さんの目に涙が浮かんでいる。涙は邪霊の好物じゃないだろうか?
「先生、大丈夫ですよ、そんなこともあるかと思って、僕、持ってきてますからっ!」
なぜ持ってきているのかわからないが、担当さんは、自分のリュックから、携帯用のソムリエ・ナイフ&フォイルカッターつきのワイン・オープナーを取り出していた。楓子さんの行動を熟知している。この位のレベルでないと、楓子さんの担当は務まらない、ということだ。
「吉井くん、私、新シリーズ書くわ! そうね、タイトルは『イタリア八十八ケ所闇遍路神話伝』ってどうかしら。あ、そうだ、今度、イタリアに取材にいかない?」
「ホントですかっ? 行きましょうよ! わーーーー、新シリーズ楽しみーー」
吉井くんの明るさが、今日も楓子さんのパワーになっている。
そして二人は富士山を横目に、ワインを飲み、静かにシウマイに舌鼓を打っていると、周りの話が聞こえてくる……。
「昔から、ドジだったわよねーー。それが住菱物産の御曹司つかまえて玉の輿だもの。ねえ、見た? これみよがしなあの大きなダイヤ……上着についているブローチのルビーはピジョン・ブラッドよ」
「やめなさいよ、英子。まあ、あのシャネル・スーツもオートクチュールでしょ? っていうか、体が細すぎて、店に吊ってあるやつじゃあわないんでしょうね」
「彼女がクラス会に来るのって、久しぶりでしょう? どう、うちの旦那の活躍は? って、みんなに自慢したいんじゃない? 息子さんも、今度、取締役に就任するみたいだし、絵に描いたような幸せ家族よね」
どうやら先ほど通路で転びそうになった美人奥様のことを噂しているらしい。
「でも、案外ああいう財界人の奥様って、本当の友達がいなかったりするのよね。それで、そろそろ私たちにすり寄ってきたくなったんじゃない? 私たちも結構、そこそこのセレブだし? 家柄的にも、さほど差はないし?」
ここで、おばさまたちの遠慮ない笑い声がどっと広がる。
先ほど楓子さんと吉井くんに、グリーン車の空席に座っていいと言ってくれた、黒のカシミアのワンピースをスラっとかっこよく着こなしている彼女が、率先して悪口を言っていた。仲間内で「英子」と呼ばれていたマダムだ。
感じのいい人だと思っていたが、ちょっとがっかりの楓子さんと吉井くんだ。
「うちの旦那なんてね、六十五で息子に社長の座を譲って、今、家でプラプラしてるから、いやになっちゃうわよ」
今度は別の奥様が、グチりだした。
「なによーー、あんな大きな家なんだから、プラプラしたってぜんぜん邪魔じゃないじゃない。しかも、稼ぐだけ稼いでくれたんだし、残りの人生は楽しまないと……お金持って、天国へは行けないわよ。いつ使うの? 今でしょ?」
「そうね、うち、不動産収入があるから、遊んでプラプラしてても一向にかまわないけど、一日中家にいられると、ちょっとねえ……」
このグリーンに乗っている白薔薇女学院OGのおばさま方は、どなたも間違いなく富裕層だ。まず元々、白薔薇女学院に通っていたという生徒のほとんどは、とんでもないお金持ちのお嬢様たちだ。入学金やらお月謝の額が、他の私学と一桁違う。
「不動産収入か……いいわね……。私は、今の世田谷のお屋敷の固定資産税を払うために、こうして書いて、書いて、また書いて……売れなくなったら、今ある土地を切り売りしていくしかないの……最後は家も没収されてしまうのかしら……。あの世田谷のおうちをこよなく愛したお祖父ちゃまに顔向けできないわ……」
楓子さんは、最後の一つのシウマイを口にいれ、下を向いてしまう。
「先生っ、元気出してくださいよっ、『イタリア八十八ケ所闇遍路神話伝』、大ヒット間違いなしですよっ。主人公は武田ゼウス神一郎っていう男性で、彼は日本人の父を持ち、母親がイタリア人のミラネーゼなんです。で、武田ゼウス神一郎は、防衛省に勤めていて、そこで日本の防衛危機管理能力の低さに不安を持ち、自らが日本を守ろうと自分の出自の半分であるイタリアに立ち、そこで神々からのパワーを授けられ、海外から迫りくる日本への脅威に立ち向かうんです……」
「吉井くん、もうすぐ名古屋よ……『天むす』……どうする……?」
楓子さんはすでに立ち上がっていた。
「いえ、先生、もうやめてっ。僕、天むすより、のんびりした旅が……」
「大丈夫よ。ここは私にまかせて」
自由勝手気まますぎる担当作家を止められないのが吉井くんの弱点だ。
しかし今回は予防線を張って、いつ名古屋駅に降りてもいいように、吉井くんはすべての荷物を手にして、乗降ドアの内側でまたハラハラとたたずんでいた。
そして、キオスクへ入る楓子さんの姿を目で追い、発車ベルが鳴り始めるのを聞きながら震えだす。ああ、もうダメ、やっぱり全然戻ってこない。一旦名古屋で降りないといけないのか……。と、思ったところで、楓子さんがのんきな顔で帰ってきた。吉井くんは初めて、尊敬する先生を、唇を噛みしめながら睨んでいた。
「僕……こういうこと、京都とか新大阪でもしないといけないんでしょうか……これ、苦行ですよね?」
グリーン車に戻った吉井くんは、珍しくストレートにグチっていた。
「吉井くん、武田ゼウス神一郎は、イタリアの港港に、ナイスバディなイタリア娘さんたちとのロマンスを繰り広げるのよ。でも、中には武田ゼウス神一郎が防衛庁(現・防衛省)のシンクタンクだっていうことを知っていて近づく悪女がいて、なんと実は、その悪女の情夫が、ソビエトの元KGBの諜報部員で、日本征服を目論んでいたの。結局、事件はたった一人のナイスバディの女が原因で、平和だった日本が次々とありとあらゆる脅威に晒されていくのよ。どう、天むす食べる? 今度、車内販売のワゴンのお姉さんが来たら、緑茶をいただきましょう?」
「先生、スミマセンっ、先生は僕の話をちゃんと聞いててくれたんですねっ!」
吉井くんは、復活した。そして担当作家さんと天むすに舌鼓をうち、のぞみはまた、先へと進んでゆく。食べている間、二人は静かだ。途中、うたたねなどしていたら、再びおばさまたちのお話しが聞こえてきてくる……。
「……京都あたりで降りて、素敵な料亭でお昼、頂きたいわ。実は私、国内旅行ってあまりしたことがなくて……少し疲れてきちゃった」
先ほどの小柄美人マダム、住菱物産社長夫人の声が聞こえてきた。
「まあ、祥子さん、ミステリー・ツアーはまだ始まったばかりよ。もしかしてもう、ご主人が恋しくなって家に帰りたい、とか?」
住菱物産社長夫人、祥子さんを囲む、通路左右を挟んで対面シートにしている計八人のマダムのグループも、盛り上がっている。
「祥子さんは、ご主人に同行して、世界中を旅されてきたものね。羨ましいわ」
「仕事で行く海外だから、そんなに楽しむ感じじゃないのよ」
「でもご主人、優しそうじゃない? よく、ビジネス雑誌で拝見するわよ。次の経団連会長候補って聞いたけど、ホント?」
「いえ、そんな、もうこれ以上、主人に忙しくなってもらいたくないわ……」
祥子さんがポツリという。
「ねえねえ祥子ちゃん、その胸のブローチ、ルビーよね? ご主人のプレゼント?」
「え、あ? う、うん……これは、タイに行った時、主人がこの原石にほれ込んで、ブローチにして私にプレゼントしてくれたの……私の宝物よ……」
「それ、ピジョン・ブラッドでしょ? 鳩の血のように、濃い赤い色……しかもそんなに大粒で……なかなか手に入るものじゃないわね」
「ええ……私、顔色が悪いから、こういう明るいものを胸元に飾って、華やかにしたらいいよって主人が言うから……」
「ステキーーーー。アタシも祥子の旦那さんみたいな人と出会いたかったわーー」
別のマダムが声を上げる。
「由紀子のご主人だって、ステキじゃない? 大手スポーツ用品店のオーナーで、ご自身もスキー、ゴルフ、カーレース、とプロ並みの腕前で、しかもご主人、いまだに、超ハンサムで、ああ、ワタシ、あの日焼けした胸に顔を埋めて眠りたいわ~~なんちゃって~~!」
マダムたちはそれぞれ好き勝手な明け透けトークを繰り広げる。
「主人、見てくれはいいけど、浮気ばっかりしてるのよ……とにかく、若い頃から女にだらしがなくて、もう、ホント、うんざりよ。で、アタシも堪忍袋の緒が切れて、何年か前に離婚しようっていうことになって、弁護士立てて調停まで行くところを、彼が土下座して謝って、もう二度としないからって、今、スマホにはGPS入れさせてもらってるし、ロックもかけさせないし、指紋認証なんてとんでもないし、いつでも見られる状態にしているし、まあ最近は、なんとか平穏に暮らしているわ……っていうか、彼ももうそろそろ年だから、男性としての機能も落ちてきちゃって、遊びたくても遊べないんじゃないかしら……フフ……」
こういう話は、楓子さんは好きだ。聞き耳たてて、合間合間にふーん、そうなのねー、とうなずいている。
「ねえ、添乗員さん、私たちこれからホントにどこに行くの? ちょっとだけでいいから、ヒント教えて? もしかして九州までいっちゃうとか?」
今度は別のシートにいるマダムが、楓子さんたちの前の席の添乗員さんのところに来て、たずねている。
もうあと十五分もすれば京都だ。
「京都とか新大阪じゃないことだけは確かよね」
楓子さんは言った。
「だって、ここにいる二十数名の中の誰かが、今、もし、洗面所とかにたっていて不在だったら、次の京都で全員があたふた降りるなんてできないし……年配になると、色々と準備が必要なの。せめて一時間前には、次の目的地をはっきりさせないと……」
「そうですね……次、京都かあ……なんか、急に焼き八ツ橋を食べたくなってきたな。僕、あの元祖ニッキ味の堅い方の焼き八ツ橋が、好きなんです」
京都の大学に通っていた吉井くんが、懐かしそうに言う。
「降りちゃだめよ。私たちはこれから、岡山から土讃線に乗って、瀬戸大橋を渡り、琴平駅に行って、讃岐うどんを食べるの。デザートには『灸まん』とか『かまど』の和菓子を頂きましょうね? その後、こんぴらさんに登頂よ。堅い焼き八ツ橋だったら、帰りの東京駅で買えるのよ?」
「……そんな……だって先生は……崎陽軒とか……天むすとか……」
二人の会話を、前にいる添乗員さんが、クスクス笑って聞いている。
「あの、お二人はお仕事でご旅行、なの?」
退屈だったのか、添乗員さんは振り向くと、シート越しに声をかけてきた。
「えっと、お仕事……ではないですね。お仕事仲間ですけど」
吉井くんが言った。
「だって、先生って呼んでらしたから、お二人とも学校の先生か何かで、修学旅行の下見にいらっしゃるのかなって……」
添乗員さんは、意外にも楓子さんたちに興味を持っていた。
「ああ……いえ、こちらの彼女は先生なんです……僕は先生のアシスタントです」
楓子さんは覆面作家なので、詳しいことが言えない。
「で、今回は、僕らの仕事がうまくいくように、故郷の神社仏閣に詣でて、運気をさらに上げようかなあ、なんて」
吉井くんは、自分の度重なる不運を笑いでごまかしつつ、添乗員さんに言う。
「あなた、四国が故郷なの?」
「ええ、香川の讃岐が実家です。今日はこれからこんぴらさんに登ったり、弘法大師空海の生まれた善通寺に行ったり……心のパワーチャージですね」
「そうよ……こんぴらさんを詣でれば、『こと開く』って聞いたもの……。私のマンネリ化した文筆業に喝を入れてもらわなきゃ……。こんぴらさんは海の神様だし、海外にも強いはず……。私、ますます、イタリアに行きたくなってきたわ……」
吉井くんが添乗員さんと話している横で、楓子さんは窓の外を見ながら、ブツブツつぶやいていた。
「善通寺もいいですよ。弘法大師空海の愛が、傷ついた心もすべて癒やしてくれます。別のお堂には巨大薬師如来坐像がありますから、なんとなく体調が悪い時にお詣りさせてもらうと、元気になるっていうか……境内はものすごく広くて、歩いているだけで、心が晴れ晴れしてくるんです……」
善通寺を子供の頃、遊び場にしていた吉井くんが懐かしそうにいう。
「金刀比羅宮に……善通寺か……」
添乗員さんは小さくうなずいている。
その時、楓子さんがいきなり吉井くんのスマホをうばい、アプリでメモを開くと、
『白薔薇の皆さまのツアーって、私たち同様、四国ですよね?』
と書いて、添乗員さんに見せた。
添乗員さんは目を丸くすると、ゆっくり通路に出てきて、自分の席を回転させて、楓子さんの側に対面シートを作ると、今度は自分の持っていたタブレットに文字を書き込み、その画面を二人に見せた。
『なぜ、四国行きがわかったんですか?』
すると楓子さんは、添乗員さんのタブレットを手に取り、そちらに書き込んだ。
『添乗員さんが、東京駅で点呼を取って、白薔薇のみなさんを次々とグリーンにお乗せになっていらっしゃる時、お持ちになっていたファイルが開きっぱなしで、つい中が見えてしまったんです。ごめんなさい、勝手に覗いて』
あんなに時間がなくて、適当に飛び乗ったのぞみだったのに、余裕で周りのことを見ていた大河先生に、吉井くんは呆然とする。
『あの……ところで、このツアーって、どなたかものすごいVIPの方が乗っていますよね?』
楓子さんはかねてからずっと気になっていたことを書いた。
『どうしてそう思われるんですか?』
添乗員さんの目は、泳いでしまう。
『だって、東京で乗った時から、このグリーン車の連結部分、前にも後ろにも、ボディガードのような男性がそれぞれ一人ずつ、待機していらっしゃるから……』
ミス・メープルは、とんでもないことを口にしていた、ではなく、書いていた。
吉井くんは、ぎょっとした顔で、楓子さんを見る。
「先生……やめて……誰もいなかったですよ……僕、誰も見てませんよ……」
『吉井くん、しゃべらないで、ここに書き込んで。他の人に、ミステリー・ツアーの情報がもれちゃうから』
楓子さんが、タブレットを吉井くんに渡す。
『ですから、ボディーガードなんて、いませんでしたから……』
『それは吉井くんが、キオスクに行った私に気をとられていたからよ。彼ら、東京駅から乗り込んでいたわよ。男性二人、一人一人が別々に行動して、添乗員さんの後ろをすり抜けていったわよ』
楓子さんの書き込みに、添乗員さんは、ものすごく動揺する。
「でも楓子さん、グリーン車って特別車両だから、グリーン車のデッキ部分に人が立っていることはできないはずです。誰もいませんよ。考えすぎです。もしかして、なにかそういうミステリー小説を読んできたんじゃありませんか?」
吉井くんが、小声で楓子さんに話す。
『もちろん、通路、デッキ、トイレ、洗面所これらすべて、グリーン車のお客さまの占有区間だから、部外者は立ち入ることはできないの。でも、私が見たボディーガードの方が、グリーン車両のグリーン券を持っていたら、連結部分にいたってかまわないのよ。あそこのデッキ、姿をかくせるところが、たくさんあるのよ』
楓子さんはさすが物書きだ。恐ろしい速さでしゃべるがごとく、キーボードを打っていく。
『吉井くん、さっき、あなたの横で転びかかった女性いたでしょう? あの方が席を立った時、ボディガードらしき男性が、一瞬、この車両に入って来たの、気づかなかった? 扉には[ミステリー・ツアー催行中]っていう張り紙が貼ってあって、この車両内はよく見えないのに、ボディーガードの方が即、この車両に入ってきたということは、この中に、防犯カメラのようなものが設置されているということよ? 彼らに、ここの情報は筒抜けなの』
楓子さんが書くと、吉井くんは黙ってしまう。
添乗員さんにおいては、固まっている。それに気づいた楓子さんは、
『あ!! 勝手な想像でモノを言って、ごめんなさい! もしかして、ボディーガードの方って、住菱物産の社長夫人さんの警護にあたってらっしゃるのかなって思って』
「えっ、そんな、まさかっ! 困るわっ……」
添乗員さんが、かなり動揺したようで、とうとう口にだしてしまった。
彼女は今、「困る」と言った。その時、楓子さんの顔がすっとミス・メープルに変わった。
『おっしゃる通り、このミステリー・ツアーは、あなた方同様、岡山で土讃線に乗り換え、瀬戸大橋を渡り、四国に向う予定でした。私たちの目的地は高知ですが……』
『高知といえば、坂本竜馬ツアーですよね?』
吉井くんが能天気に書き込む。
『あの……もしかして、そのボディーガードのような彼らも、私のファイル……覗いてましたでしょうか……』
『覗かれたら、マズいんですか?』
楓子さんはタブレットに書き込みながら、大好きな事件の匂いを嗅いでいた。
『行き先が知られてマズい場合は、目的地を変更すればいいじゃないですか。元々ミステリー・ツアーですから、簡単なことです。高知はやめて、私たちと一緒に、こんぴらさんと善通寺、行きません? 運気もあがりますよ』
楓子さんも能天気を装いながら書き込んでいる。
『私……讃岐界隈には……詳しくなくて……』
添乗員さんは、添乗員という職についている割に、四国に詳しくなさそうだ。
『こちらの彼、吉井遼くんって言うんですが、讃岐の地元民ですから。彼が添乗員になりますよ?』
楓子さんが書くと。吉井くんが小さな声で「まかせて」と言った。
『でも、今夜の讃岐界隈に泊まるホテルとか、レストラン……これからどうやって予約したらいいのかしら……』
彼女は明らかに、ボディーガードの男性たちを撒いてしまいたいようだった。
『夜は、高知に行って、元々予約していたホテルとレストランをご使用になればいいじゃないですか。讃岐から高知って、そんなにめちゃくちゃ遠くありませんから。二時間かからないんじゃないかな』
四国民の吉井くんが書いた。
『いえ、キャンセルします。行く先がバレてしまっては、ミステリー・ツアーになりませんので』
添乗員さんはきっぱりと書き込んだ。
『でも、当日キャンセルって、難しくありません?』
吉井くんはそれはありえないと思った。きっとほぼ満額とられる。
『キャンセル料を払うこと自体は、問題ありません。このツアーの参加者はどなたもそういうことは、気にしませんので。それより、もっと楽しい充実したツアーを求めているはずです』
添乗員さんは真意をごまかしながら書いているのが、楓子さんにはわかる。
『そうですか……費用は……考えなくていいのですね……』
書きながら吉井くんは驚いた。しかし、よく考えれば、元々、グリーン車を一両まるごと借りきってしまうセレブ・ツアーだ。ホテルやレストランのキャンセル料など、取るに足らないことなのだろうか……。
『ボディーガードの方を、撒きたいのですよね……?』
楓子さんが、とうとう核心を書き込む。
すると、添乗員さんが、息をのんでうなずいた。
『あの、実はこちら、(趣味で)探偵もやっている先生だもので……よろしかったらお力になりますよ』
とうとう吉井くんが楓子さんの裏の素性を書き込んだ。
『ボディーガード……ではなく、彼らがしていることって、尾行です。尾行されていること、添乗員さんは、お気づきじゃなかったんですね……?』
楓子さんが、書いた。
『そんな……尾行だなんて……』
タブレットに書き込む添乗員さんの右手は、そこで止まった。
そしてその後、「どうしよう……」と、つぶやいた。
『でもあの……これってすべて私の勘違いかもしれません。私、実は本業が物書きだもので、ついつい人より想像力が豊かになってしまって……』
楓子さんは、添乗員さんをこれ以上驚かせまいと、さらに素性を明かした。
しかし、添乗員さんは動揺しすぎて、楓子さんが物書きであろうがあるまいが、そんなことはまったく頭に入っていなかった。とにかく平常心に戻ろうと必死になっている。
『あの、では添乗員さん、よろしかったら僕が、臨時添乗員になります。今日はおまかせください。まずは、大人数でも入れるおいしいうどん屋さんをご紹介します! 今から、予約も入れておきますから大丈夫です! それから、こんぴらさんに登りましょう! もし、必要でしたら、隠れ家的ないい温泉旅館も知ってますから、そちらも手配します!』
勤め先の翔岳館で培った、常に仕事関係者に機転を利かせるプロの技を持つ吉井くんが、添乗員を買おうという。
『旅は道連れです。僕らをグリーン車両に乗せて頂いたお礼をさせて下さい!』