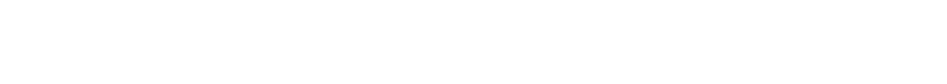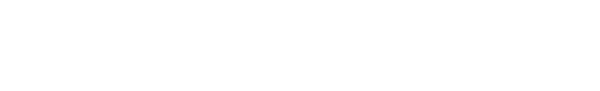WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 瀬戸内海の秘密』 柊坂明日子
-



第3回「海、空、そして自由の島へ」
「吉井くん、助けて……私、もう、これ以上、ムリ……」
楓子さんは、今、七八五段ある金刀比羅宮の階段のほぼラストの部分でへこたれていた。そこは薄暗く、他の参拝者の姿もない。
「先生、頑張って下さい! 白薔薇女学院のOGマダムたちはもうとっくに頂上に着いているんですよ! 楓子さん、彼女たちよりずっと若いでしょう!?」
吉井くん率いる白薔薇女学院御一行さまは、岡山から土讃線に乗り換えると、瀬戸大橋を渡り、四国に上陸すると、高知駅とは逆方向の琴平駅へと向かった。スケジュールが変更されていることに気づかない白薔薇のマダムたちは、終始ハイテンションで、わいわいがやがや、旅を楽しんでいた。
その元気マダムたちは、全員がとっくに七八五段ある金刀比羅宮の参道を登り切っている。セレブの奥様たちは、常日頃からジムなどにいったり、近所をジョギングしたりして健康管理に余念がないので、ハードな金毘羅宮詣にも音をあげなかった。
「だって、吉井くん、私、原稿書き上げたの、ほんの二日前よ、ずっとずっと不規則な生活して、夜もろくに眠れず、体調は万全じゃないの。私、もう、ここでいいわ。悪いけど、頂上の御本宮神札授与所で、私のために『商売繁盛』のお札をもらってきてくれる?」
「そんな、あと百段ちょっとですから! ほら、階段の上に最後の鳥居が見えますでしょう? その先が御本宮なんです。もったいないです! 僕、おんぶしますからっ!」
吉井くんはうずくまる先生を必死で励ます。
「ううん、もう、こんな私は放ってていいから、頂上の白薔薇女学院のみなさんをケアしてあげて……それがこの土地で生まれ育った真の添乗員としてのあなたの務めよ」
「いや、僕、それ以前に、先生の担当でしょうっ!?」
今や吉井くんは、白薔薇女学院ミステリー・ツアーを率いるリーダーだ。金毘羅宮参拝前にお連れした地元の人しか知らないうどんの名店では、マダムたちの感動の声が響き渡っていた。あっという間に、吉井くんはおばさまたちのアイドルと化した。
と、この時、楓子さんが座り込んでいる階段脇の薄暗い雑木林に一陣の風が吹いた。その風が楓子さんの額の汗をスーッと冷やしてくれる。
「あっ! 先生、今のわかりました? 神風ですよ。神様が楓子さんを応援しているんです。ここ、そういう風が時々吹くんです。先生、諦めちゃいけません! オニバです、オニバ!」
吉井くんは、フランス語を使い、なんとか楓子さんを立ち上がらせると、後ろに回り、その背を両手の平でググっと押した。
「えっ、吉井くん、体が軽いわっ! そのまま押してくれたら、私、登れそう!」
御本宮前のこの最後の階段は、『御前四段坂』と呼ばれていて、石段は四段階に分かれていてそれぞれに踊り場があるが、とにかく角度が急で、このラスト百段ちょっとの参道が一番ハードだ。最後の最後で信仰心を試されているかのようだ。
そして頂上まであと七、八段、というところで、白薔薇女学院のマダムたちが、上がってくる楓子さんに気づき、四、五人が下りてきてくれると、左右から楓子さんの腕をグイッとつかみ、御本宮前まで連れて行ってくれた。
そこは、ただただ桃源郷のような爽やかな風が吹いている。梅や桃や早咲きの桜などの香りが、神前に漂っている。
「ありがとう、みなさん、ありがとう、吉井くん……私、あきらめないでよかった」
御本宮の前で、楓子さんは一瞬、涙ぐんでしまう。
「さ、先生、お詣りしましょう? ここも階段が急だから気をつけて下さいね」
神前へと、吉井くんと二人、細くて狭い十段ばかりの急階段を上がっていく。
そして揃って、二礼二拍手一拝のご挨拶……。
楓子さんも吉井くんも、それぞれがここまで来られた感謝の気持ちを金刀比羅宮の神様にお伝えしていた。
「よかったわ……ちゃんとお詣りできて……私、ここに来るまでは『商売繁盛』とか一攫千金とか、ギラギラ考えていた心底ダメな私だったけど、今はもうここに来られたことがただただ感謝ね……今、ウソみたいに体が楽だわ」
そして二人は参拝を終えると、清々しい気持ちで、本宮右手にある展望台へと向かった。その眼下には淡い桜色をした春霞の讃岐平野が広がり、形のいい讃岐富士はぽこんとそびえ、長閑な風景が人々の心を癒している。その遠くには瀬戸内海。青い空に青い海がつながっている。この景色を見て初めて、なぜわざわざこの高い山の中腹にお宮が造られたのかがわかる。
「でこちゃん、遼くん、一緒にお写真、撮りましょう?」
添乗員さんが、二人に声をかけてくれると、白薔薇女学院マダム二十数名と楓子さんと吉井くんを入れた全体写真を一眼レフのデジカメで撮ってくれた。
楓子さんはでこちゃん、吉井くんは遼くんと呼ばれ、今やすっかり白薔薇女学院ツアーの一員だ。
記念写真の後、マダムたちはみんなで神札授与所に行き、御神籤を引いたり、お守りを選んだり、と、またわいわいがやがや楽しそうだった。その後ろ姿はまるで女学生だ。
「楓子さんも、お札、お授けしてもらったらいいですよ」
同じく神札授与所前で、立ち尽くす楓子さんに、吉井くんが言う。
「いえ、私はいいわ。だって私は吉井くんがいるだけで、商売繁盛だもの」
「先生~~っ! 僕、これからもっともっと頑張ります! 新シリーズの『イタリア八十八ケ所闇遍路神話伝』頑張りましょうねっ?」
吉井くんは、嬉しくてつい絶叫してしまう。
しかしその楓子さんの視線は、神札授与所前であれこれ盛り上がっている白薔薇学院のマダムたちの行動にいっている。その目は完全にミス・メープルだ。
「先生、どうしたんですか? 何か気になることでもあるんですか?」
「うん……みなさん、各種小さなお守りをお授けしてもらっているんだけど、お二方だけ、木のしっかりした御守札をお授けしてもらっていたわ。なんか、本気のお願って感じよね」
「ですから、やはり先生もここで『商売繁盛』の木の御守札をお授けしていただいたらいかがです? せっかくここまで登って来たんですから」
吉井くんは、次の新シリーズをまた大ヒットさせたい。
「うん……でも、そのお二方の御守札、どちらも『海上安全』なのよね」
「海上安全、何がおかしいんです? こんぴらさんは海の神様ですから、『海上安全』でいいじゃないですか……。ここまで来たら、海の神様頼りですよ」
「住菱物産は……もちろん海外で大きくビジネスを展開しているけど、別に今、海上安全じゃなくてもいいんじゃないかしら……」
「えっ、何っ、あの住菱の社長夫人の祥子さんが海上安全のお札を授けてもらったんですか? それのどこが気になるんですか?」
「なんか……本気の度合いが違ったの……。最初、祥子さんは、『諸災削除』の御守札を見てて……でも、結局『海上安全』を選んだの」
「それの何が何なんですか? 先生だって『商売繁盛』を授けてもらいたかったり、やっぱり『身体健全』がいいかな、とか迷ったりしますでしょう?」
ここで『良縁成就』とか言わないところが、気遣いの吉井くんだ。
「そうね……迷うわよね……うん、迷うわ……守札料も二千円と安くないものね」
楓子さんは、自分の中の違和感を消し去りつつあった。
「それより、楓子さん、次は善通寺です! 弘法大師空海のパワーを一身に授かりにいきましょうよ! なんか僕、もうここまで登っただけで、すでに今、怖いくらいにパワーアップしています!」
そんな吉井くんに頷きながら、楓子さんは神札授与所に行くと、『身体健全』と『厄難消除』のお札を授与してもらった。『身体健全』は自分のため、そして『厄難消除』はいつも苦労ばかりかけてしまう担当さんのためだった。
*
その夜、大浴場を出たところにあるリクライニング・マッサージチェアに、浴衣姿の楓子さんが座ってブルブル揺れている。
「はい、これ、先生。喉乾いたでしょう? いいお湯でしたね」
そこへやって来た同じく浴衣姿の吉井くんが、楓子さんにミネラルウォーターのペットボトルを渡している。
「吉井くん、あなたのご実家、ここから目と鼻の先なのに、一緒に旅館に泊まらせてしまって、ごめんなさいね……私、あなたのご両親に申し訳ないわ……」
そういう楓子さんの声まで、マッサージチェアの振動で震えている。
「大丈夫です、明日、行きますから。だって、このミステリー・ツアー、事件の匂いがプンプンなんでしょ? そう言われたら、僕も気になって、実家になんて帰れませんよ。それに、担当作家さんを置いて自分だけ実家に戻ったら、うちの親が怒ります。二人ともタイガーショーの大ファンですから。全巻読んでますよ」
吉井くんはニコニコしながら、自分も楓子さんの隣のマッサージチェアに座って、スイッチをオンにした。このマッサージチェアのお陰で、こんぴらさん参拝の階段でうけた筋肉痛が、みるみる和らいでいく。
「ありがとう……私、もしここで事件に巻き込まれたら、それをいつかきっと、作品に反映させるから……もちろん、事件を未然に防ぐのが一番いいのだけどね……」
楓子さんは、ブルブル揺れながら、その目は、女湯の入り口を見つめている。
今日の午後の金毘羅宮参拝の後、吉井くんは、白薔薇女学院OGの皆さんを、土讃線で移動させると、次に弘法大師空海誕生の地である『善通寺』にお連れし、彼女らはまたまたそこでパワーアップした。
弘法大師ゆかりの聖地である善通寺には、本尊・薬師如来を安置する金堂に、高さ四十三メートルの五重塔、そして樹齢千数百年といわれる大楠の木がそびえている。この金堂や五重塔は国重要文化財、大楠は香川県の天然記念物だ。お大師様の生まれた地である西院、そして唐から帰朝したその空海が建立した東院をゆっくり散策すると、誰もが日常のせわしなさから解き放たれ、心身に英気がみなぎってくるのを感じる。
今宵マダムたちはみんな、吉井くんが急遽予約を入れてくれた讃岐の老舗温泉旅館でのんびりしている。ここは、観光ガイドブックなどに宣伝を載せない知る人ぞ知る名旅館だ。
「さすが瀬戸内海のすぐそばのお宿ね。お夕飯のお刺身とかお魚料理が素晴らしかったわ。それにつけくわえ讃岐牛のフィレ・ステーキまで……お米もおいしかったし、どれもこれも、東京では頂けない大ご馳走ね……吉井くんは素敵な土地で生まれ育ったのね」
楓子さんは、温泉に入る前に頂いた晩御飯に感動していた。旅先でその土地の旬のものを頂ける贅沢に、楓子さんはもちろん、白薔薇の皆さんも幸せを感じていた。
「讃岐牛や讃岐米はそれほど生産量がありませんので、四国内でほぼすべて消費されちゃうんです。ですから東京の人にはあまり知られてません。お魚はどの季節も、おいしいです。たぶん、普通の旅館に泊まっても、おいしい魚料理が味わえます。香川県民はグルメですから。たいていどこで何を食べてもハズレがありません!」
吉井くんは故郷に誇りを持っている。
そしてまたしばらく二人、無言でマッサージチェアに揺られていると、ふっと楓子さんが、身体を起こした。
「どうしました……? アイスクリーム食べます? 棒がついたハーゲンダッツの自機ありますよ。えっと、種類はザッハトルテとマロンタルト……かな……」
吉井くんも身体を起こした。
「ハーゲンダッツはまた後で……私、もう一回、温泉に入ってくるわ……」
見ると、あの小柄美人の住菱物産社長夫人、祥子さんが一人そっと、女湯ののれんをくぐって、温泉に入っていった。
「でも、先生、そんなに何度も何度も温泉に入ると、湯あたりしてのびちゃいますよ。大丈夫ですか?」
「大丈夫、気をつけるわ……どうしても、気になることがあるの」
壁の時計は今、午後十一時三十五分を示している。
ここの温泉は、零時でいったん終了だ。
「じゃあ、あの、僕、ここで待ってますね……なるべく早く、戻ってきてください」
うんうん、とうなずきながら、楓子さんがまた女湯に入っていく。
その後ろ姿はもう完全にミス・メープルだ。ご一緒できない吉井くんは残念でしかたがない。
そして温泉終了まであと三分、というところで、まず祥子さんが出てきた。
そして、その後でそっと、楓子さんが出てきた。
その顔はすっかり曇っていた。湯あたりして具合が悪いのかもしれない。心配した吉井くんは楓子さんにかけよっていった。
「いいお湯だったわーー、さすが老舗旅館ねーー。吉井くん、棒つきのハーゲンダッツ食べましょうかっ!? 私的には、ザッハトルテかな~~。アプリコット・ジャムが挟まってて、おいしーの! 気分はオーストリアのウィーンね」
楓子さんが、とってつけたような笑顔で、吉井くんに言う。これは明らかに何かあって、ショックを受けている時の反応だ。ゼンゼン目が笑ってない。
そして、近くのベンチに座ると、訝し気に遠くを眺めていた。
「どうしました?」
「やっぱり祥子さんにボディーガード、はりついている。さっきから男性が一人、エレベーター脇の自販機の横に立っていたけど、祥子さんが温泉から出たのを見て、また姿をかくしたわ。たぶん、祥子さんはもう、自分がつけられていることを知っている……知っていてもう、諦めているのよ……」
楓子さんは、そう言うと落ち込んでいた。
「あのね……吉井くん……」
楓子さんは、いきなり声をひそめると、吉井くんの耳元である事実を伝えた。
その顔はものすごく悲しそうだった。
「ええ……そんな……まさか……」
吉井くんは絶句した。
「かごの中の鳥よ……」
楓子さんはつぶやくと、一瞬にして目に涙をためた。
「祥子さん、今日の午後、善通寺で楠木でできた念珠の腕輪のお守りをお授けしてもらっていた。善通寺にゆかりのある楠木の腕輪なの。『般若心経』の題字が一玉一玉に彫り込んであるやつよ。それをお授けしてもらうとすぐに身につけていた……」
そこへやってきたのは、添乗員さんだった。浴衣姿で、バスタオルを胸に抱きしめている。
「まあ、遼くん、でこちゃん、今日はありがとう。素敵な旅館で、みんな大満足よ。ご飯もお酒もおいしかったし。で、私も今から、温泉に入ろうかなと思って……」
しかし、もうそこには清掃中の札がかかっている。
「あらやだ! 温泉、もう終了なの? 私ったら……何をやっているんだか……」
添乗員さんの割に、うっかりしている。
「あの、柏木さん……もう少し、私たちにお話を聞かせて頂けませんか……私、このままでは、東京に帰れません。何か……私たちが、お手伝いできることって、ありませんか?」
楓子さんが真顔で柏木さんにたずねた。
添乗員さんは柏木さんという。もう、楓子さんたちは、名前で呼べるほど親しくなっていた。
「ここには、防犯カメラもありませんし、盗聴マイクもありません。今、見たところ尾行の男性たちもいません。でも、尾行の男性らは、どうやらこの旅館に泊まっているようですね。彼らはプロです。なかなか撒くことはできないですね……」
楓子さんが言うと、柏木さんはため息をついてうつむいてしまう。
「あの……白薔薇の皆さんは、明日は、どのようなご予定ですか……?」
楓子さんは聞いた。
「それが実は……まだ決めてなくて……仕方がないから、昨日予定していた高知へ行こうかと思って……」
柏木さんは、すでに万策尽きたかの口調だった。
「あの……これは私の本当に勝手な想像なのですが……柏木さんは祥子さんと個人的にお親しくて、柏木さんは祥子さんに、このツアーを使ってどこかに逃がしてほしいと、頼まれているのではありませんか?」
衝撃的なことを楓子さんが言うと、柏木さんは驚きすぎて言葉がでない。
「な……なんで、そこまで……わかるの……」
柏木さんの声は震えてしまう。
「ごめんなさい……今、私、温泉に入って……祥子さんの身体を見てきたんです。 湯煙で、見えにくくなってはいたけど……彼女……手首にリストカットの痕とか……背中に青あざとかがたくさんあって……でも、温泉に入りたかったのね……誰もいない時間帯を選んで……静かにお湯につかってました……」
楓子さんは途中、ポロポロこぼれてくる涙を止められないでいた。
それを浴衣の袖で拭っても拭っても、涙がこぼれてくる。
「でこちゃんの言う通りよ。そうなの……祥子は結婚した当初から、ご主人から暴力を受けていて、離婚したいって何度も言っても、聞き入れてもらえなくて。祥子の両親はもう亡くなってしまったから、頼る人がいなくて……今の息子さんは、愛人さんの子供なの……その彼を育てたのは、祥子だけど……。それだったら、愛人さんを奥様にすればいいのに、ご主人は祥子に執着して、自由にしてくれないの。もう、祥子の身体も心も限界なの。逃がしてあげたい。祥子、このままじゃ死んじゃう……」
親友を思う柏木さんの心の叫びが、伝わってきた。
「逃がすと言っても……あんな頼りない祥子さんが一人で逃げられるものですか? それとも、もしかしてどなたか祥子さんを支えて下さる方がいらっしゃるの?」
楓子さんの問いに、「それは大丈夫」と、柏木さんが静かにうなずいた。どういうお相手なのかは言わなかった。それを言えるほどにはまだ、楓子さんたちは信用されていない。尾行されるくらいのことが起こっているのだから、どこにどんな敵が潜んでいるのかわからない。容易に何もかを打ち明けてしまうことができないのだろう、と楓子さんは察した。
「電車はだめ……バスもだめ……じゃあ飛行機はどうです……? もしかして、高知へ行くのは、高知空港が目的でした?」
ミス・メープルの助手である吉井くんは、さすがにするどく切り込んだ。
「その通りよ。当初は高知空港が目的だったの。本当は国際便も飛ぶ高松空港がよかったんだけど、それだと怪しまれると思って、わざと国内便のみの高知空港を目的にしたの。高知からまず国内にあるどこか大きな空港へ逃げてほしくて」
柏木さんは『逃げる』という言葉に力を込めた。
「ということは、目指すは福岡とか関空とかですかね……」
吉井くんは、うーん、と考えてしまう。
「あ……そうだ……電車だめ、バスもだめ、飛行機もだめ、ということならば……!」
吉井くんは、突然こぶしを握った!
この担当さんは気づいていないが、ご本人、危機的な時にはいつもねらわずして物凄いことを考えだす能力に長けている
「僕……明日、お墓参りに行こうと思ってたんです。うちの一族は、元は瀬戸内海の小さな島の出身で、そこに今も先祖代々のお墓があるんです。通常、丸亀港からフェリーでその島に渡るのですが、明日は僕、小型フェリーをチャーターします。皆さんもご一緒に、瀬戸内海の離島ツアーいかがです? 尾行もさすがにそこまではついてこられないのでは? うちの島についたら、祥子さんには、そのフェリーで、別の港に逃げてもらいます。新岡山港とかはどうかなと思うんです。で、そこからタクシーで岡山桃太郎空港に行って、飛行機に乗ればどうでしょう。ここは、国際線も飛んでます。そして、残った白薔薇の皆さんには、引き続きミステリー・ツアーをうちの島で、楽しんでいただけたらと……。今きっと、桜が満開です……すごく綺麗なところなんです。実は隠れたお花見スポットです」
吉井くんのプランに、楓子さんはにっこり。柏木さんは希望の光を見出していた。
翌日、快晴。吉井くんは二十五人乗りの小型バスをチャーターしてきた。
旅館の裏手に停めたそれに、白薔薇女学院のみなさんが今、乗り込んでいく。
「みなさん、おはようございます。本日のミステリー・ツアーは、これから二十分ほどかけ丸亀港へと参り、そこでチャーターした高速船に乗り、瀬戸内海の島へと、お花見ツアーに参ります! 本日、桜は五分咲き、花が一番初々しくて美しい時です」
吉井くんはガイド役も引き受け、マイク片手に通路に立つと、白薔薇のマダムたちに、本日の予定を告げている。
「遼くん、お花見楽しみにしてるわ! お昼ご飯とかも、期待していい?」
旦那さんが浮気ばっかりしているスポーツ用品店のオーナーの奥様である由紀子さんが言った。
「おまかせください! 友人のご両親が琴平で老舗割烹料理屋をやっているので、そこに頼んでおいしい二段重ねお花見弁当を作ってもらいました!」
吉井くんは、昨夜ほとんど寝ていない。ありとあらゆるツテを使って、お友達やバス会社、高速船チャーター会社に今日の予約をお願いしていた。
「これから行く島は過疎で、島民は年々少なくなるばかりです。あるのはただただ雄大な自然と桜、そして瀬戸内海です。その絶景を是非堪能して頂けたらと! ちょっと大げさかもしれませんんが、高台に登って見る眺めはまるで南仏のニースです。目の前に広がる海は地中海かと!」
吉井くんが言うと、割れんばかりの拍手が小型バス内に響き渡る。
「ワタシ、新婚旅行、南仏だったのー」とか、
「ウチの娘、フランス人の男性と結婚して、今、ニースに住んでいるのー」とか、おばさまたちはどんなことにでも大盛り上がりだ。
バスはすでにもうゆっくりと発車している。長閑な一般道を走り出す。
「東京で、人、人、人、にまみれて、慌ただしく生活をしている私たちにとっては、人のいない離島なんて何よりの息抜きだわ。今日は命の洗濯をさせてもらうわね」
旦那さんが六十五歳で定年して、息子に社長の座を譲ると、今は不動産収入で悠々自適の弘美さんが言う。
楓子さんはバスの最後部に座り、追ってくる車はないか、後方を見ている。朝なので、出勤途中のマイカーが走っているだけだ。楓子さんが見た尾行の男性が運転している様子はない。しかし、彼らはそんなに甘くないはずだ。
そうこうしているうちに、小型バスは丸亀港へと到着した。
白薔薇女学院のマダムたちは、バスを降りると、吉井くんの後をついていく。海に近づくにつれ磯の香りが充満してくる。
チャーターした小型高速船は、丸亀港ですでにエンジンをかけ待機していた。
「さ、皆さん、足元に気をつけて、乗船してくださいね」
マダムたちが船に乗り込む間、吉井くんと楓子さんは、白薔薇のみなさんのための二段重ねお花見弁当やら、飲み物、お菓子等々を、次々船内に積み込んでいく。
大丈夫。誰も、つけていない。全員を船に乗せれば、あとはもう何の問題もない。
楓子さんと吉井くんは、ドキドキしながら、素早く行動を起こしていく。
そして追手を撒いてくれるよう尽力してくれた小型バスの運転手さんにお礼をいい、いとまごいをすると、楓子さんと吉井くんは高速船に乗り込んだ。
船は白い泡をたて、丸亀港を離れて行く。
すぐにあの雄大な瀬戸大橋が見えてくる。岡山から四国に渡った時に土讃線で走った瀬戸大橋だ。まさかその瀬戸大橋を海から眺めることになるとは思わなかった。今は朝日を浴びて銀色に光っている。遠くの山々が薄いピンクに染まっている。
その景色を見ながら、楓子さんも吉井くんも、これなら大丈夫、と心から安堵した。
そこへやってきたのは、柏木さんだ。
「でこちゃん、遼くん、ありがとう、本当にありがとう……もう大丈夫ね」
柏木さんの目に、涙がたまっている。
その柏木さんの後ろに隠れるようにして立っているのが、祥子さんだった。
「あの、まったく見知らぬお二人だったのに……こんなにお力になっていただいて、本当に何とお礼を言っていいか……」
祥子さんは、花柄の絹のワンピースに、ベージュのコートを羽織っていた。コートの襟には、あの美しいルビーのブローチが光っている。
「旅は道連れです。あの……祥子さん、幸せになって下さいね」
吉井くんが言う。
「パスポートはお持ちですよね?」
楓子さんが言った。
「はい。これだけは忘れず、握りしめてきました」
祥子さんが斜め掛けしたポシェットに手を置いた。その腕に、弘法大師ゆかりの楠木の念珠の腕輪が見える。
「そうだ、祥子さん、スマホの電源、切ってますよね?」
吉井くんが聞いた。
「あの、私、実はスマホは持ってないの」
祥子さんが顔を曇らせて言う。
「ご主人が、持たせてくれなかったのよ。誰とも簡単に連絡がとれないようにして。だから、祥子と連絡を取るのって、いつも本当に大変だったわ。このツアーも白薔薇女学院のクラス会だから、なんとかやっと許可が出て、旅行に出してもらえたんだけど……まさか、尾行されているとは、思わなかったわ……」
柏木さんが祥子さんの代わりに事情を話す。
「そういうことですか……いやあの、スマホを持ってたら、GPSとかで、所在を確かめられちゃうので」
吉井くんは、念には念をいれる。
「潮風が気持ちいいわ……。私、こんなに息を深く吸い込んでいるのって、久しぶりな気がする……」
祥子さんは儚げな顔でそれでも笑った。
この同級生が次の島で逃避行を企てようとしているとは夢にも思わない白薔薇女学院の明るいマダムたちは、今、船内に入って、そこでまたみんなでわいわいがやがや大盛り上がりだ。船内は、瀬戸内海の美しい景色を堪能するより、女子校トークに花が咲いている。
一方、楓子さんはずっと黙っていた。海の様子を見たり、時々空を仰いだり、珍しく何か緊張しているような様子だった。
「あっ、楓子さん、見えてきましたよ。ほら、あそこ……見て、海岸沿いにずらーっと桜が咲いているでしょう? ああ、よかった、今日、お花見日和ですよ……かなり満開に近いなあ」
丸亀港を出て二十分ほどで、吉井くんは先祖代々が眠る島を見つけると、指さしていた。
「うわあ、綺麗ね……素敵だわ……今日は暖かいし……吉井くん、冴えてるわ。きっと、白薔薇のみなさんにも喜んでいただけるわね……この景色、すごく贅沢よ」
デッキに立つ楓子さんが、吉井くんに微笑む。
港はもう目の前だ。何十本もの桜並木が出迎えてくれる。
「ここの港前の広場って、夏にはやぐらを建てて今でも盆踊り大会をやるんですよ。盆踊りといっても、東京でやるような楽しいお祭りではなく、本当にその年、島で亡くなった新盆の方々を、お迎えするある意味神聖なお祭りなんです。島を出た親族の皆さんが、その盆踊りのために、一斉に里帰りしてくるんです。夏は本当に島がにぎやかになります。ああ……僕、本当に久しぶりだな……ここに戻るの……」
吉井くんが、到着した故郷の島に目を細める。
そうこうしているうちに、船内にいた白薔薇女学園のマダムたちが、わいわいはしゃぎながらデッキに出てきた。みんなしっかり下船の準備ができている。
「見てよ、桜、満開じゃない! あんなに見事な桜、久しぶりに見るわ!」
マダムの一人が、感動している。
「ここって、お花見のために作られた広場みたいね……なのに、お花見客がまったくいないなんて……贅沢だわ……ここ貸し切り状態よね?」
また別のマダムが歓声を上げる。
「皆さん、気をつけて下船してくださいね」
吉井くんはタラップを降りるマダムたちの下船を手伝っている。
「でこちゃん、ありがとう……私、勇気を出して、もう一回、人生をやり直してみる」
最後に船内の残った祥子さんが、楓子さんの両手を握る。
「さ、私も船を降りて、みんなにお別れを言ってくるわ」
と、祥子さんがタラップを降りたところで、いきなり空に暗い影が走ったと同時にバリバリ、バタバタ轟音が鳴り響きだした。巻きあがる突風。やっと開いたばかりの桜が、舞い散ってしまうほどの強風だ。
「な、何なの、あれ!!」
楓子さんが指さした先に、ヘリが一機、飛んでいる。今、頭上でホバリングしている。そして港の広さが災いして、そこに悠々と着陸しようとしている。
「どうして!? どういうこと!?」
楓子さんは祥子さんを見た。
祥子さんは怯えた顔で、震えだす。
そして着陸したヘリから、立派な身なりの紳士が下りてきた。
「しゅ、主人……だわ……」
「だって祥子さん、スマホ持ってないでしょ? なぜこの場所がバレたの?」
あっ! と、楓子さんは叫ぶと、祥子さんのルビーのブローチをはずした。そして、その裏を見ると、そこには、小さな金属のようなものが埋めこまれていた。
「祥子さん、これGPSがついているわ! これで、行く先を特定されていたのよ!」
祥子さんはあまりのショックで、デッキでうずくまってしまう。
そしてスーツ姿のご主人が、一歩また一歩と近づいてくる。とうとうタラップの下まで来た。
「祥子、そろそろ東京に帰ろうか? こんな離島に来ても、何もないだろう?」
優しい笑顔、優しい声。
「でこちゃん……ごめんね……ここまでしてくれたのに……」
祥子さんは、立ち上がって、真っ青な顔でタラップを降りようとする。
「行っちゃだめ。このままこの船で逃げて。後はまかせて」
楓子さんは、祥子さんの手をとって、デッキへ連れ戻そうとする。
「ううん、もうだめ……もう逃げられない……」
祥子さんは恐怖のあまり、一歩も動けなくなる。
その時、楓子さんが叫んだ。
「英子さんも、早く上がって来て、早く二人で逃げてっ!」
楓子さんは、英子さんを呼んだ。
英子さんと言うのは、あののぞみのグリーン車内で、祥子さんの悪口を言っていた彼女だ。メッシュ入りのベリー・ショートで、黒のカシミアのワンピースをスラっとかっこよく着こなし、爪のネイルが美しかった人。その英子さんは、今日、動きやすいパンツ・スーツをはいていた。
「英子ちゃんも逃げること……知っていたの……?」
祥子さんは、驚いていた。
「二人でこんぴらさんで『海上安全』の御守り札を授けてもらってたじゃない。二人でこれから、海を越えて、遠い国へ行くんでしょう? お大師さんの楠木の念珠の腕輪も、二人、お揃いよね? 大丈夫よ、こんぴらさんもお大師さんも、二人の行き先を守ってくれるわ。勇気をだして!」
添乗員の柏木さんが口には出さなかったが、祥子さんを支えてくれる人が、英子さんだった。きっと英子さんは、どこで盗聴されているかわからないから、わざと祥子さんの悪口を言って不仲をアピールしたのだろう。
でも楓子さんは、二人の香水が同じディオールのプアゾンであることに、新幹線の中でもうすでに気がついていた。
「祥子、行こう!」
港にいた英子さんが、いそいでタラップをのぼっていく。
しかし、それを阻もうとしているのが、祥子さんのご主人だ。
白薔薇女学院のマダムたちは、何が起こっているのかわからない。みんな、ざわめくだけだ。
「さ、祥子、帰ろう。もう、こんなわけのわからないミステリー・ツアーは、ここでおしまいにしなさい。クラス会だからって、しかたなく許可したが、一応、尾行をつけてみたら、その彼らを撒こうとして、いったい何をやろうとしているんだ?」
とうとうご主人が、祥子さんの腕をつかんでデッキからタラップへと、引きずり降ろしてしまう。
「やめて……もう、いやです……もう、自由にして下さい、もう放して!」
あのか弱い祥子さんが、声を振り絞って叫んだ。
「東郷さん、お願い、もう、祥子を自由にしてあげて、あなたがやっていることは犯罪です。このままじゃ祥子は死んでしまう!」
英子さんが、祥子さんから旦那さんを振り払おうとした。
東郷というのが祥子さんの旦那さんの苗字だ。
「何を言ってるんだ、君は、どけっ!」
住菱物産の社長ともあろう男性が、英子さんを突き飛ばし、タラップから落としてしまう。それだけでなく、今度は祥子さんの髪をつかみ、ヘリに連れて行こうとする。
と、その時だった。
カシャ、カシャ、カシャ、カシャ、カシャ、カシャ、カシャ、カシャ!
ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ……。
白薔薇マダムたち全員が全員、バッグからスマホを取り出し、住菱物産の社長の暴挙を撮影し始める。その姿はまるで、拳銃で狙いを定めている警官隊だ。マダムたちは、スマホから手を離さず、写真と動画撮影を続ける。
「なんなんだ、お前らは! やめろっ!」
動画では、この社長の暴言も録音される。
驚いたのは、楓子さんと吉井くんだった。白薔薇女学院のマダムたちは全員、これが祥子さんと英子さんの逃避行ということを知っていて、初めから協力していた。
そして、それを最後まで楓子さんたちに打ち明けられなかったのは、祥子さんの命がかかっているからだ。祥子さんをご主人から切り離さないと、もう、彼女にはこの先がないのだろう。二人の逃避行を失敗させることはできなかったのだろう。楓子さんたちには感謝しているが、最後の最後で信じるのが怖くて、念には念を入れざるを得なかったのだろう。それだけ祥子さんには、危険が迫っていたことがわかる。
「東郷社長、おばさん、なめんなよ。この動画を拡散させたら、お宅の会社、いっぺんに株価が下がって、おしまいだからね! この三月って、決算期じゃなかったの?」
旦那さんが浮気ばかりしている大手スポーツ用品店のオーナーの奥さんである由紀子さんが、社長に大声で言った。
「あと、うちのスポーツ用品すべて、お宅の会社との取引やめさせてもらうからね。その事実だけでも株価ダダ下がりだからね! うちのスポーツ用品店の力がどんだけ強いか知ってるよね?」
ここにきて由紀子さんは、めっちゃくちゃ強かった。
そして、同時に一歩前へ出てきたのは、添乗員さんの柏木さんだ。
「今の動画にもろもろの画像持って出るところに出れば、祥子の完全勝利ですよ。それに、祥子の身体の傷、すべて写真で撮っているから、それも大きな証拠になるからね! 私、今まで離婚裁判やってきて負け知らずだから、今回は眼に物言わせてやるわ! 私、こういう証拠が、喉から手が出るほど欲しかったんだよね」
何と柏木さんは、弁護士さんだった!!
「こちとらね、祥子とは、白薔薇幼稚園からもう六十年の付き合いなんだよ。アンタより長いのっ! あの、丸々ぷっくりしたりんごのほっぺの祥子をこんなに痩せさせて……傷つけて……許さないからね!」
怒りを爆発させる柏木さんも白薔薇女学院のOGだった。そのくせ、他の白薔薇マダムたちのことは、まるで初対面のように、終始ふるまっていた。
こうしている間も、他のマダムらは、社長が祥子さんを無理やり連れて行こうとする様子をスマホで撮り続けている。
「それだけじゃ、すまないよっ!!」
次に声を上げたのは、行きののぞみで、祥子さんの近くに座って、しきりにピジョン・ブラッドのブローチを褒めていたまどかさんだ。
「東郷社長、うちの息子、今、『週刊文潮』の編集部で働いているの。こりゃ、春から縁起がいいわ、息子に手柄をたてさせてもらえるみたいね。『文潮砲』ドカーンと一発、二発、三発、連続で打ち上げますよっ!!」
『週刊文潮』とは、政治家、経済人、タレント、スポーツ選手など著名人のスキャンダルをスクープさせたら、ぴか一の週刊誌だ。この週刊誌が次から次へとスキャンダルをスクープし続けることを『文潮砲』と呼び、失態を犯した彼らが引退、辞職に追い込まれることは必至だ。
そこで楓子さんも、遅まきながら加わった。
「あの、このブローチ、GPS組み込ませてますよね? そこまでして祥子さんの行先が心配だったら、なんで初めから奥様を大事になさらなかったんですか?」
それを聞いた白薔薇のマダムたちは、えええ~~~っ!! やり方きたな~~い!! と、呆れかえってしまう。
「えっと……このブローチも、離婚の時のいい証拠になると思います。ここまでして人を束縛するなんて、どうかしてるもの」
そう言って、楓子さんは、ピジョン・ブラッドを柏木さんに渡した。
「おかしいと思ったわ。柏木さんって、添乗員さんなのに、温泉終了の時間も知らないし……それに、アラカンで現役の添乗員さんって、すごく珍しいし、旅行代理店のバッジも偽物みたいだったし……。そっか、弁護士さんだったのね。弁護士さんで白薔薇女学院OGの祥子さんの大親友だったのね」
楓子さんが言うと、
「ごめんね、こんなに手伝ってもらっているのに、話せないことばっかりで……」
と、柏木さんが謝った。
楓子さんと吉井くんは、「いいえ」と首を横に振っていた。
「東郷さん、いいかげん、祥子を自由にしてあげて。あなた、みっともないですよ、立派な大会社の社長さんなのに」
突き飛ばされて砂埃まみれの英子さんが立ち上がり、社長に言った。
「祥子、目を覚ましたらどうだ? お前が私と離れて、この先、生きていけるわけないだろう? どこへ行って、どうやって生きていくんだ? ボーっとしたお前に何ができるんだ?」
住菱の社長が祥子さんの腕をつかんでどうしても離さない。
「もう、やめて下さい……。あなたのところには、戻りたくない……」
初めて祥子さんが旦那さんの目を見て、きっぱりと言った。ここには二十数名の幼稚園からの仲間がいる。
「ふざけんなっ、お前、今までさんざん贅沢をして、いい暮らしをしてきただろっ!」
そう言って、社長は祥子さんをとうとうひっぱたいた。
「やめてちょうだいっ!」
英子さんの悲鳴。
白薔薇マダムたちは今もスマホの動画を撮り続ける。どう考えても東郷社長の負けだ。
「はい、これ、ご記入お願いします」
柏木さんが、緑の文字で書かれたのB4の用紙を取り出して、社長に渡した。
離婚届だ。
「あんた、ふざけんな! 他人が夫婦のことに口をだすな!」
そう言って、その紙を空高く飛ばしてしまう。
しかしまた、柏木さんはもう一枚、離婚届けを出し、それを社長に渡す。
「社長が離婚を承諾してくれたら、ここでの動画も画像も一切流さないでおきます」
弁護士の柏木さんが言った。
「そうね、ワタシも、うちの息子にいい仕事させたかったけど、『文潮砲』もしばらくは、打ち上げないでおくわ。ここで離婚届を書いてくれるならね」
まどかさんが、忌々し気に言った。
「ああ、でもウチは、悪いけど取引終了ね。これだけはやらせてもらうわ。だって何のお咎めもなかったら、あなた、身に沁みないでしょう?」
大手スポーツ用品店オーナーの奥さん、由紀子さんが言った。
だんだんに社長の顔が、曇ってくる。そしてとうとう祥子さんの手を放した。
「祥子、お前、後悔するぞ。このままで済むと思うなよ」
そう言う社長に、柏木さんがファイルを差し出し、それを台にして、離婚届にサインをするよう促した。彼女は、三文判の印鑑もちゃんと用意して持っている。
「英子ちゃん!」
祥子さんが、英子さんに駆けていく。
「祥子、ごめんね、もっと早く一緒に逃げればよかったね……こんなになるまで苦しませて……私、早く行動しなかった自分が許せない」
英子さんが泣きながら、祥子さんの手を取った。
「さ、祥子さん、英子さん、船に乗って! 後の手続きはまかせて!」
柏木さんが、二人を高速船へと急がせた。
「お前たち、ふざけんなよ、オレはどこまでも追っていくからなっ!」
社長が、船に乗り込む二人にまた暴言を吐いた。
それをまた白薔薇のみんなが、スマホで撮っていく。
「あのー、今の、脅迫だからね。もし、二人に何かあったら、ワタシら絶対に絶対に絶対に許さないからね。あ、ちなみに、うちの旦那、東京地方検察庁のバリバリの検事正だから」
そう言うのは、行きののぞみで、英子さんの隣に座り、祥子さんは細すぎて、シャネル・スーツはオートクチュールでしょう、と相づちを打っていた人だ。彼女も悪役を一役買っていた。
「くそっ! お前らみんなくそだっ!」
社長はそう言うと、今度は離婚届をビリビリにやぶいた。
でもまた、柏木さんが次の用紙を彼に手渡す。
「ああもうチクショウ! なんでだよっ……」
社長は、動き出そうとしている高速船に向かっていった。
「祥子、頼むよ、行かないでくれよっ、俺が悪かったよ……もう、辛い思いはさせないから、行かないでくれっ! 反省しているっ!! 今度こそ本当だっ!!」
なんと、社長が涙ながらに祥子さんに謝っている。
「ごめんなさい、正幸さん、今までありがとう、でもさようなら。加寿子さんを、大切にしてあげてね。加寿子さんなら、あなたと添い遂げられるわ。もう、彼女を待たせないであげて」
加寿子さんとは、祥子さんが育てた息子さんの本当の母親のことだろう。
「私、子供は生めなかったけど、正志さんを育てられたことは、幸せだったわ。母親をやらせてくれて、ありがとう。そのことは感謝しているから」
正志さんとは、その加寿子さんが生んだ息子さんのことだ。
「そんなこと言わないでくれよ。正志だって、お前のことを本当の母親のように、なついていたじゃないか。頼むよ、行かないでくれ、オレ、心を入れ替えるから! も一度だけ、チャンスをくれよっ!!」
「正志さんももう立派に育ったし……でも、ごめんね、あと、どれくらいあるか知らないけど、私、残りの人生は、本当に好きな人と過ごしたいの。この六十年、ずっと好きだったの……これ、最後のわがままだから……私、他に何もいらないから……」
船がとうとう動き出した。港から離れて行く。
「祥子、英子、幸せにねーー。落ち着いたら、ワタシら遊びに行くねーー」
「何かあったら、絶対また力になるからね、私たちの六十年のこの絆、まだまだ続いていくんだからねーー!」
白薔薇マダムたちが、声の限りをつくして、二人にさよならを言う。
「でこちゃーーんっ、遼くーーんっ、ありがとーー! 私、この御恩、絶対、絶対、忘れないからねーーっ!」
そう言うと、祥子さんが大粒の涙を流し始めた。子供のように、わんわん泣き始めたのがわかる。
そんな祥子さんを、英子さんがそっと後ろから抱きしめる。
二人が桜色の春霞の中、小さくなっていく。白薔薇幼稚園だった頃の二人のように、その姿は小さく小さく消えていく。
「Bonne chance(グッド・ラック)。お幸せにね……」
楓子さんは、いつまでも手を振りながら、そうつぶやいた。
先ほど、ヘリのプロペラで舞い散った桜が、今、海面にキラキラ浮かんでいる
春の旅立ち--------卒業。