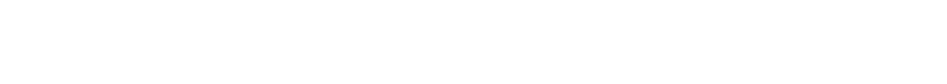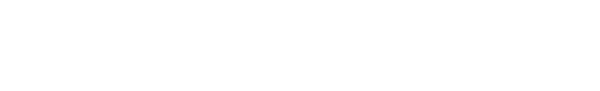WEB連載
『おばさん探偵
ミス・メープル 瀬戸内海の秘密』 柊坂明日子
-



第1回「呪われた男」
三月。
東京は世田谷区、固定資産税が天文学的な数字のお屋敷町に、春の兆しがあふれている。梅の開花が終わると、今は桃があちこちでいい匂いをただよわせ、それと競うように、桜の蕾も膨らんでくる。
三ヵ月前の冬至の頃、午後四時前にはもう薄暗く、あたり一面陰鬱な影を落とし、小学生は歩いてはいけないと言われた森野楓子さんのお屋敷前の裏通りも、今は日が延びて、冬枯れだった樹々の隙間から、キラキラした陽光が降り注いでいる。
「ああ……春だわ……春ね……原稿も書きあがったことだし、なんかこうパーッと外に出て、リフレッシュしてみたいわ。旅行なんかに行きたいなー。でも、一人で行くのもつまらないし――」
このアラフィフの楓子さんは、長年の夢だった絵本作家になりそびれ、気づくと男性名の『大河ショー和』(短く『タイガーショー』)で、SFバイオレンス・アクション・エログロ・超ハードボイルド作家になっている。代表作である「新宿魔法陣妖獣伝」シリーズが、この世の不条理に疲れたサラリーマンのおじさんたちの間で、出版不況を吹き飛ばす大ヒットだ。楓子さんは、その第八巻目をようやく書き上げ、今、ホッと一息ついている。
その楓子さんのお屋敷は、都内ではありえない広さを誇り、高塀で囲まれたその内側は、鬱蒼とした樹々に囲まれ、外から見るとそこだけ完全に森林地帯だ。近所の子供たちは、その森の奥には魔女が住んでいると信じている。
が、森の奥にあるのは、昭和の初期に建てられた、イギリス、チューダー様式のお洒落な洋館だ。洋館の正面玄関前は花壇になっていて、もうすぐチューリップが咲き乱れる。この洋館は、あちこちガタがきていたが、昨年、屋根やら壁やらを直したので、あと二十年くらいは問題なく住めるだろう。
屋敷まわりの煉瓦の塀に関しては、漆喰から直したのであと五十年は持つヨ、と左官さんのおじちゃんに太鼓判を押されたが、現在すでにアラフィフゆえ、あと半世紀、ここで生きぬく気がしない楓子さんだ。
「ここはもうすぐハウステンボスよ。いえ、そんな小さなことを言ってちゃだめ。だって、私、去年の年末、あのダダ寒い中、死ぬほどチューリップの球根を植えたじゃない。今年、うちの洋館前はオランダになるのよ。オランダって言えば、ゴーダチーズね。ああ……なんかいい白ワインにゴーダチーズが食べたくなってきちゃった。そうだ、お洒落マダム御用達のKINOKUNIYAへ行って、ゴーダを買うのよ! パリッとしたバゲットとかも買って、今夜は一人オランダ祭りね!」
花壇前にたたずむ楓子さんは、夕日を一身に浴び、大きく息を吸った。楓子さんは独り暮らしが長いので、このように独り言が多い。
と、その時だった、遠くにバーバリーのトレンチを翻す長身の男性の姿が見えた。
「やだ、どうしよう、もしかしてヒュー・グラント? それとも、ただの吉井くん?」
ヒュー・グラントとはイギリスの有名な俳優さんで、楓子さんは昔から彼の大ファンだ。ジュリア・ロバーツと共演した『ノッティング・ヒルの恋人』の中のヒュー・グラントが今でも理想の男性らしい。
一方、ただの吉井くんとは、小説家である楓子さんの担当さんで、吉井遼という。現在、二十八歳、翔岳館の『ナイト・ハンター・ノベルス』の編集者だ。まだ若いのに、いい仕事をする。そしてとても紳士で優しい。
楓子さんがメガ・ヒットを出し続けられるのも、すべてこの吉井くんのお陰である。
しかし、つい昨日会ったばかりの吉井くんが、なぜまた、この屋敷に現れているのか、楓子さんは瞬時に不安を覚えた。
「か、楓子さ~~ん……」
いつも、顔を見せてくれる時には、かならず有名菓子店のケーキだのクッキーだのチョコだの、あるいは肉まんだのコロッケだのを差し入れてくれるはずの吉井くんが、今日は空手でヨロヨロやってきた。
それだけで、何かものすごい緊急事態であることを、楓子さんはひしひしと感じざるをえない。
いつも爽やか、かつ上品なイケメンだったのに、今日の吉井くんは、トレンチコートのボタンを一つずつかけちがえ、髪は春風に舞い上がりくしゃくしゃ、とどめに唇は紫だ。白目部分は泣いたのか、かなり衝撃的なことがあったのか、血走っている。
「まずは落ち着きましょう、吉井くん。どうしたの、会社をクビになったの? クビになっても大丈夫よ。だって吉井くんは、もともと京都の大学で何かすごい薬の研究をしてたのよね? 有名な教授が院に来てくれって、泣いてたのんだのも知ってるわ。今からでも遅くないわ。会社をクビになったら、これから院に行って、日本の苦しむ人たちを救ってあげればいいだけ! もし、ノーベル賞を取ったら、私も授賞式に参列させてね。北欧ってまだ行ったことがないの」
楓子さんが中途半端に励ますと、吉井くんはわっと涙を流した。
「吉井くん、泣いちゃだめっ、泣くとさらに、不幸がふりかかってくるのよ! それはいつも言ってるわよね? 邪霊の好物は涙なのっ」
楓子さんはスピリチュアル色を強めて、担当さんを励ました。
「違うんです、いや、違わないかもしれない。僕、もう、きっとクビですっ」
「だからどうしたっていうの? 話してくれなきゃ、わからないじゃないっ!」
「僕、昨日、楓子さんからお預かりしたUSB、失くしてしまったんですーーっ」
吉井くんは、イケメンのバーバリー姿のまま、チューリップ畑の横で、膝をついて土下座の形になる。その肩はプルプル震えていた。
「えっと、吉井くん、USBってなんだっけ、『ウソ、ソンナ、バカナ』ってこと?」
「そんなようなものです、楓子さん、ううう~~、ごめんなさいっ、あの、楓子さんのパソコンの中に、今回の原稿残ってますかっ?」
「えっ、原稿残ってるって、どういうこと? 私、昨日、吉井くんに原稿が入ったフロッピーを渡したわよね?」
楓子さんは、ほんの二、三年前まで、頑なにワープロで原稿を書いていた人だ。フロッピーというのは、あの懐かしい九センチ四方の薄いフロッピー・ディスクのことだが、パソコンを使い始めた今でも楓子さんはその名残で、USBをフロッピーと呼んでいる。
「あの、楓子さんって、USBっていうか、えっと、そのいわゆるフロッピーのバックアップ取っている人でしたっけ?」
「やだもう、吉井くん、USBとかフロッピーとかバックアップとか、カタカナばっかり。専門的過ぎてよくわからないし……」
楓子さんはとにかく精密機器に弱い。だからスマホも持っていない。ガラケーもだ。家の電話は、留守録、ファクシミリ機能のいっさいついてない、昭和な黒電話だ。
「専門的じゃないですよ、ただの英語です。しかも楓子さん、ほぼバイリンガルでしょう?」
「えっと、(三カ国語喋る)トリリンガルかな? ほら、私、こう見えて実はフランス語もできるの。スペイン語もけっこう勉強したから、(四カ国語喋る)クワドリンガル?」
「今、問題はそこじゃないです……僕もうホントに、どう先生に謝っていいのか、わからないですっ。先生がっ、先生が必死の思いで書いた原稿をどうやって失くすことができるのか、僕もうダメですっ。大学院になんて、戻れません、僕、讃岐の実家に帰って、一から出直しですっ」
「吉井くんとは去年、瀬戸内海を横断して行く八日間の済州島、釜山のクルーズに一緒に行った仲なのに、お別れなのね、実家に帰っちゃうなんてさみしいわ。私これでまた、独りぼっちね……」
「いや、そうじゃなくて、先生、あの、僕、ずうずうしいお願いだとは思いますけど、先生のパソコン、チェックさせて頂いてよろしいですか? ワードのところに、おそらく、今回、先生が書かれた小説が、まだ残っていると思うんです。えっと、それを僕のパソコンに送信させていただいて……」
「吉井くん、その前にお茶しない? さっき焼いたフルーツケーキがあるけど、すごくおいしいの。紅茶飲みましょう? 私、喉が渇いちゃたし、おなかもすいたの。でん六のピーチョコが食べたい」
「僕はもう、先生のところでご馳走になれるような身分じゃないんですっ。人としてはもう完全に終わってますからっ。あの、とりあえず、先生のパソコン、開かせていただいてよろしいですか?」
「私のパソコンを開けば、吉井くんの悩みも解決するの?」
「だといいのですが……」
「じゃあ、まずは悩みを解決してから、あとでオランダ祭りする? あ、でも、ゴーダチーズも買いに行ってないし、バゲットもないし、ただの祭りね……でも、一緒にゴハンを食べて帰ってくれると、嬉しいわ……」
その二十分後--------吉井くんは、中国の極厚絨毯、緞通のしきつめられたサロンの中央にあるマホガニーの丸テーブルについていた。
「うわーー。ビーフシチューだ~~。黒毛和牛の塊が、トロトロに煮込んであるーー。肉がおっきいーー。僕、今日、ここに来てよかったです~~」
編集者としては絶対にやってはいけないことをやってしまったにもかかわらず、吉井くんは今、恵比寿顔で、楓子さんとちょっと早いディナータイムを過ごしている。
「やだもう、吉井くんったら、USBを失くしたなら失くしたって、そう言ってくれればいいのに(いや、彼はずっとそう言っていた)。私、しっかり者だから、ちゃんと複製くらいとってあるわよ~~」
楓子さんは、USBを失くされたことなど気にもせず赤ワインを開け、作りすぎて冷凍してあった自信作のビーフシチューを吉井くんと食べている。パンがないので、ビーフシチューの中に焼いたお餅をIN(イン)だ。
「複製……複製か……複製って言えば、話は早かったんですね……。でも、本当にごめんなさい。僕、昨日、先生からUSBをお預かりして、安心してしまって、会社の自分の机の上に置いたところ、亜蘭編集長に呼ばれて打ち合わせして、席に戻って、帰宅して、次の日会社に行ったら、もうどこをさがしてもUSBが見あたらなくて、気づくと机の引き出し前に置いていたゴミ箱も空で、なんかの拍子にUSBが机から落ちたのかもしれないし、でも、夕方くるお掃除会社の女性が、そのゴミをかたずけちゃって、僕がそれに気づいたのが今日のお昼過ぎで、ゴミ集積所までいっても、そこには何もなくて……ホントにすみませんでしたっ」
「いいのよ、原稿くらいで、そんなにあわてないで。命とられるわけじゃないんだから」
「でも僕、これが亜蘭さんに知られたら、間違いなくクビですっ。担当、変えられちゃいますっ」
「えっ!! いやよっ、担当変えられたら、私が困るわっ。私、吉井くん以外の編集者さん、みんなコワクてキンチョーちゃって、打ち合わせなんて無理だからっ」
ここにきてようやく楓子さんは、吉井くんの痛恨のミスが、ダイレクトに自分に降りかかってくることに気がついた。
「それより僕、このところどうも、うっかりミスが多くて……先週なんて、自分のマンションの鍵をなくして、夜中、鍵のレスキュー隊に来てもらって、ようやく部屋に入れたと思ったら、下の下の階の人が小火を出して、消防車が消火に来たのはいいけど、うちまで水びたしになって……それだけじゃないんです! 先月は電車でうたたねしてたら、ポケットから財布すられました。たいした額は入ってませんでしたけど、カードとかを止める作業が大変でした」
「吉井くん、それは、うっかりミスじゃないわよね……明らかに災難よね?」
「僕、どうも年末年始頃から調子悪くて……初夢なんて、なんかこう暗いトンネルを延々と歩いていて、いつまでたっても光が見えてこないんです……」
「ところで吉井くん、今年、初詣はいったの?」
「えっと、あの……先生の家で酔いつぶれてて……。でも先生は朝一番に氏神様にお参りに行ってましたよね……」
「あ、そうね、吉井くん、年末からうちにいたわよね。で、今年のお正月もご実家には帰らなかったのね……? って、引き留めたの、私よね……?」
「先生のせいじゃありません。帰りたかったんですけど、新幹線の切符が取れなくて。満席でした……。それに、先生と恒例の行く年来る年パーティーもしたかったし」
「で、初詣には行ってないのね。それで、ご実家にも帰ってない……」
「実家には去年の秋に帰ったきりです。シルバーウィークの時、ちょっと」
「ちょっとって、何日くらい?」
「一泊二日です」
「とんぼ返りね。その時、お墓参りとか、してきた? 秋のお彼岸シーズンよ?」
「あ、いいえ……。僕が最後にお墓参りしたのは、いつだったかな……一昨年のお盆かなあ……いや、一昨々年か?」
「それだわ」
「えっ。それだわ、ってどういうことですか?」
吉井くんに、緊張が走る。
「年末年始、お盆、時にはゴールデンウィークまで吉井くんの自由を奪っているのは、この私。しかも去年のクルーズでは、瀬戸内海を航行しているにもかかわらず、香川が故郷の吉井くんを、ご実家にも寄らせてあげられなかった……。それを知ったご先祖様や土地の神々様、特に弘法大師は、どれだけ寂しい思いをしたかしら……。ということで、吉井くんには、今、お墓参りや神社仏閣への御礼、そしてきちんとしたご挨拶が必要なの!」
「えっ、な、何、それ、どういう意味ですかっ?」
「いい? 出版界には魔物が住んでいるの。そこにいるのは、うまくいく人間と、うまくいかない人間。そこには妬み、嫉み、恨みの嵐が常に吹き荒れているのよ。その嵐に巻き込まれないためにも、人は神社仏閣に詣でて、当たり前の日々を送れることにまずお礼を申し上げ、日々降りかかってくる悪いものを祓っていただくの。そして、同じく大切なことは、お墓参りね。ご先祖様に、いつも力になって守っていただいていることへの感謝の気持ちをしっかりと伝えるのよ。それができないでいると、一つまた一つと色々なことの歯車がかみ合わなくなり、気づくと不運の連鎖に見舞われているの……」
吉井くんはみるみる青ざめていく。それに気づいた楓子さんの飼い猫、アメショー柄のシンプキンが、七キロ強の体でジャンプして、吉井くんの膝に飛び乗ると、即、お腹を見せ、「モフっていいよ」と吉井くんを励ましている。
「いい、吉井くん、自宅の鍵をなくし、小火にまきこまれ、財布をすられ、USBを失くす。この一、二ヵ月でこんなことが立て続けに起こって、偶然って言える?」
「言えません。僕、ここ数ヵ月、もしかしなくても絶不調です」
「行きましょう」
「えっ、行くってどこに?」
「今、お彼岸よ。お彼岸って言ったら、どこに行くの?」
「お墓参りです……」
「そして、あなたの故郷、香川県は讃岐界隈にある最強の神社仏閣は?」
「弘法大師空海がお生まれになった『善通寺』と『金刀比羅宮』いわゆる『こんぴらさん』です」
「明日出発ね」
「あ、いえ、明日は金曜日ですから、僕、会社に行かないと」
「何言ってるの? 明日は彼岸の入りよ。明日行動しないでいつするの? ご先祖さまは、かわいい吉井くんに会いたがっているのよ? 亜蘭さんには、私が電話しておくわ。私、新作が書いてみたいので明日から取材に出ます、つきましては吉井くんに同行お願いしてよろしいでしょうか、って」
「えっ、先生、もしかして『新宿魔法陣妖獣伝』じゃなくて、別シリーズを書いて下さるんですかっ!」
「オニバ、思い立ったが吉日ね」
「先生はオニババじゃないですよ、優しい、素敵な女性です。薄暗いスナックとかで見たら、三十代でも通ります!」
「吉井くん……オニバよ、On y va. オニヴァ。フランス語でレッツ・ゴーっていう意味なのに……」
「そ、そうですよねっ、先生、トリリンガル、じゃなくて、クワドリンガルでしたね。すみません、僕、ホント、こういうミスが多くて……わかりました、行きましょう! 僕、この旅で、生まれ変わってみせます!」