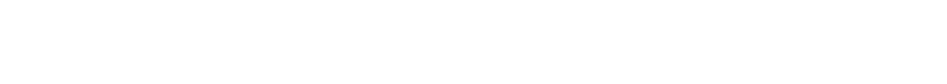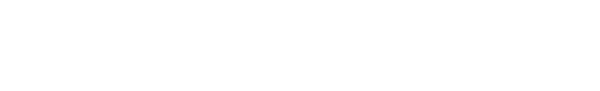「なぞとき遺跡発掘部」ショートストーリー
-


冬休みは何をしますか?
日向夏
灯里が研究室の冷蔵庫を開けると、白い世界が広がっていた。
「これ、何すか、先輩?」
「コンビニ限定スイーツだ」
「いや、見たらわかるんすけど……」
問題は量だ。一つ二つ、三つ四つではない。白い大福が山になっていた。
「これ、今話題になっているやつじゃないすか? よく売り切れている」
「ああ、苦労した」
カチカチとキーボードを打ちながら応答する古賀先輩、二十三歳、身長百九十オーバー、体重八十五キロである。
「先日売り切れていたから補充のトラックが何時に来るか確認して、向かった。このふんわりとろりとした生クリームと求肥との食感がまたいいんだ」
買い占めを行う先輩のやりかたはどうなのだろうか、と思いつつも、確かにこれは買い占めしたくなるくらい美味しそうだ。
「一つください」
「……一つだけだぞ」
間が空いたことには突っ込まないでおくのが優秀な後輩というものだ。灯里は、クリーム大福を頬張る。小さな大福は二口で胃袋に収まった。
「ふう、うまいっすねえ。これ」
「そうだろそうだろ。クリームと求肥が共に口の中でとろける感じがいい」
「もう一個」
「ダメな」
断られた。
仕方なく、冷蔵庫のドアのポケットに入ったペットボトルを取って、ロッカーの荷物を肩にかける。
「じゃっ、先輩。良いお年を!」
すちゃっと敬礼する灯里。
「ああ。そういや、冬休みは帰るって言ってたな」
「はい。正月くらいは帰って来いと言われたので」
とはいえ、灯里の実家は同じ県内だ。帰らなかった理由は、家族と不仲とかそういうものではない。バイト先のシフトの関係上、帰れなかったなどということもある。
「先輩は残るんでしたよね? 福岡にいるなら、お正月に私のバイト先に遊びに来てくださいよー」
「結局、バイトするんだな」
「むしろ年末年始はかき入れ時っすよ。クリスマスはケーキで、その後、神社で巫女さんのバイトっすね。見ます? 灯里の袴姿、見ます?」
「あー、うん、時間があったらなー」
またキーボードを打っている。さも、興味ないと言わんばかりの態度だ。
「……先輩は正月どーするんすか?」
「基本、親戚同士の集まりがあるし、周りの家は高齢化が進んでるんで、色々駆り出される。っていうか、ばあちゃんが勝手に俺をレンタルしてる」
小柄でしたたかな古賀先輩のおばあちゃんを思い出す。
「うわあ、お気の毒様っすね」
「年末は餅つきが二件、大掃除が三件」
灯里は黙って、手のひらを合わせる。
「じゃあ、彼女とデートなんてできないっすねえ」
「いないこと知ってて言っているだろ?」
むっとする古賀先輩。
よし、と灯里は拳を握る。
クリスマス前にフリーは嫌だと、即興でカップルを作る男女は多い。パワーはゴリラだけど、顔面レベル高めの古賀先輩は、けっこうもてるのだ。
「じゃあ、お正月は年末の疲れを癒すために寝正月ってところっすね」
「まあ、そんなところ、と言いたいが、ちゃんとメインイベントがあるぞ」
「めいんいべんと?」
何だろうと首を傾げると、先輩はパソコンで検索した画面を見せてくれた。
「教授とこれに行く」
「甘木バタバタ市……」
お祭りだ。バタバタとはデンデン太鼓のことで、子どもの顔をしたものが売られている。
「教授と……」
「ああ。関係者に教授はよく呼ばれるからな」
検索結果のホームページを見ると、祭りの歴史について書かれてあった。
「考古学ってほど古くないっすよね?」
「そこは言うな」
「前は、おしろい祭かなんかに行ってませんでした?」
あさくら市にある奇祭の一つだ。顔に白粉を塗りたくるお祭りでこれまた歴史があるらしい。
古賀先輩が敬愛を通り越して溺愛していそうな西枝教授の専攻は考古学、時代は弥生から古墳時代である。
だが、一般人から見たら歴史の先生と言えば、過去すべて網羅しているとお考えなのだろう。
来賓としてのご招待と言うより、あくまで「来れたら来てねー」というお誘いの域だが、呼んでいただけるだけでありがたいと、お人好しな教授は必ず顔を出すのである。
灯里は先輩が見せてくれた画面をもう一度見る。
「へえ、天然痘除けに子育て祈願っすか。あれっすよね。天然痘って、今はもうなくなったっていう病気でしょ?」
「日本では、一九五五年に根絶されたと言われているな。でんでん太鼓は、子どもが天然痘にかからないようにと願ったものだが、それから、産室に飾ると見目好い子どもが生まれ、家に飾れば幸運が訪れる、と言われるようになったとのことだな」
「すげーっすね、先輩。ちゃんとホームページの内容通りっすよ」
賢そうに見えるアイテム、眼鏡は伊達ではない。
「あっ、お菓子も名物みたいですね」
灯里は古賀先輩からマウスを奪い取り、カチカチページを移動する。
「帰らなくていいのか?」
「……おっ、もうこんな時間だ。って、自転車で間に合いますかね?」
「甘鉄か?」
甘鉄、甘木鉄道はあさくら市の鉄道である。甘木は、あさくらの市町村合併前の名前だ。その名の通りのローカル線である。
「いや、高速バスっすよ。十二時三十五分発、逃すと向こうのバイトに遅れちゃいますね」
「間に合わんだろ。ってか、バイトもう入れてるのか?」
呆れ顔の先輩はパソコンを閉じて、ポケットから車のキーを出す。
「ほら、遅れたら相手先に悪いだろ。早く行くぞ」
「先輩、愛してます!」
灯里が古賀先輩に抱き着こうとすると、がしっと頭を掴まれ、距離を取られた。「んー」と唇だけ突き出している灯里の立場はない。
「いらん、そんなのいらんから」
「えー、ひどーい」
「それより高速インターに、自転車置き場はあるのか? 帰り乗るだろ」
「折り畳みなんで大丈夫っす」
前にバイト代のかわりにもらった物だ。使い勝手がいい。
「いくぞ」
「はい!」
灯里は荷物を肩にかけて、古賀先輩の後ろについていった。